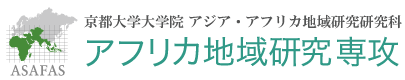*インタビュアー:I
I:ではまず、最初に木村さんの研究内容を教えてください。
木村:そう漠然といわれると(笑)
I:では研究を始めたきっかけなどでも。
木村:僕は京大の理学部に1978年に入学したんですが、当初は、数学をやろうと思ってたんですね。でも、2回生になったころから、何だか「俺はこういうことをやっていていいのか」という気がしてきました。ローマクラブが『成長の限界』という本を出したのが、70年代の初めだったと思うけど、今で言う地球環境問題の始まりでしたね。人口問題、公害問題とかも含めて、このまま行ったら危ないという話になっていたんですね。そういうことに興味をひかれたりして。人口問題を解決するには、子どもの数を少なくしなくちゃいけないことは明らかなのだけど、じゃあ、子供を減らしてどうなるのか?結局どういうふうに生きるのがいいことなんだ? とか、まあ、非常にベタな言葉で言うと、人間にとって幸せとは何なんだといった(笑)、最終的にそういうことを考えないといけないのかな、と思うようになったんですね。あと当時、友達が近衛ロンド(今の京都人類学研究会)に顔を出していて、来てみるか?と誘われてそれに行ったり、調査をちょっと手伝ったりしているうちに、人類学に興味を持ちました。自分が、もやもやと思っていることを知るために、何をやったらいいのか正直わからなかったのですが、なーんか人類学っちゅうもんをやったら何でもやれるのかなと。その間口の広さと、あとフィールドに行ってなにかやるという方法論というのが、当時としては非常に新鮮だった。それで、その人類学をやってみようかという気になったんですね。
理学部にも人類学の講座があるっていうことを知って、そこに伊谷純一郎先生がおられた。そこはサルの研究の中心地でしてね。同時に狩猟採集民の研究もやっていたし、伊谷さんはそのころトゥルカナっていう牧畜民の研究もされていました。それで理学部の大学院を受けようかなという気がしてきたんですね。どうしようかなと悩んで、伊谷さんの研究室に話を聞きに訪ねて行ったのが、4回生の始めだったか。当時はトゥルカナを始められていたので、先生の『トゥルカナの自然誌』っていうのを最初に読んで、それから有名な『高崎山のサル』とかね。読むとすばらしい文章を書かれるというのがわかって、非常に感激して、これだけすばらしい文章を書ける人だったらすばらしい研究者にちがいないと思って、この人のところでやりたい、と思ったわけです。
当時、ちょうど日経新聞の「私の履歴書」というコラムに伊谷さんが連載されていて、その中に、日本のサル学の始まった宮崎県の幸島というところに今西錦司先生に連れていかれて、そこでサルを見たときに,いままでの青春の迷妄を抜けて「俺はこれをやろう」と心が決まったと、そういう文章が載っていたんですね。それに感激したというところもあって、ここ受けようと思ったのですが…。院試が9月にあるんですよね、受けようと決めたのが6月で(笑)。それから3か月間、生物学の勉強をがーってやって、人類学の勉強もやって。4回生のときには何とか1次は通ったのですが、2次試験で落ちた。でも、もう一回来年受けてみようと決めて。そのあと、太田さん(現、アフリカ専攻の太田至教授)たちに、山地放牧のウシの調査で隠岐島に連れて行ってもらいました。
I:それは浪人中に行ったのですか?
木村:浪人が決まった後に。太田さんがお金を取ってきたので、誰かこないかと声をかけてくれて、その調査が初めてのフィールドです。自分でほとんど旅行もしたことなかったのに、いきなりフィールドに行って、そこでかなりカルチャーショックを受けました。それまで僕は茶道部でお茶やっていたのに、フィールドやる人ってわざと下品にするとこあるじゃない(笑)?向こう行ったら一軒家を借りて5,6人で下宿というか、共同炊事みたいなことして、「お前、味噌汁を作れ」と言われて、作り方なんて知らなくて、具に何を入れたらいいんですかと聞いて笑われたりね。昼は自分たちで作った握り飯を持って山に入って、個体識別したウシがどこで何をしているか調べるというフィールドワークを2週間くらいかな、やりました。次の年は一生懸命勉強して、何とか人類進化論研究室に合格しました。
修士のときは日本でやりましたが、博士課程になってフィールドやるんだったらアフリカに行け、お前ザイールに行けと言われて。
I:最初はどのような調査をされたのですか?

写真 1
木村:日本ではトカラ列島というとこで調査してたんだけど、最初の一年は悲惨な状況でした。帰ってきてゼミで喋っても誰も面白いって言ってくれないし、あくびをし始める人が出たりして、もうだめなんじゃないかと思ってね(笑)。2年目でなんとか頑張ってやったのが、島民の対人関係のデータだったんです。それまで、植物採集とか魚の認識とか、いろいろやったのですが、結局ものにならずに、結局、誰と誰が一緒に酒飲んでいるかというデータがものになって修士論文を書きました。(写真 1)

写真 2
アフリカでも最初から対人関係をやりたいっていう気はあったんですよね。すると、どろどろした対人関係があるところがいいんじゃないかという話になって、「木村は農耕民の社会に入れよう」という話になったらしい。ではザイールのワンバに入れようということになって。ワンバはボノボの調査隊がずっと入っていたし、生態人類学者の先輩がすでに二人調査していたんですね。人類学者は僕が三人目だったのだけど、僕の場合は生態人類学もやるけど、やはり人々の社会関係がやりたいなと思っていました。行ってみたら最初はなかなかしんどかったですね。現地語のリンガラ語もほとんど喋れないし。喋れない、すると連中の言ってることがわからない、わからないと喋れないということで、悪循環みたいな感じで。結局、独りでほっぽりだされて1か月くらい、誰も日本人とかいない状況で過ごすと、なんとか喋れるようになってきました(写真 2)。
そのあとに講談社の野間奨学金というのに当たって、それで2年行けました。最初の1年は、いろいろやろうとするのだけど、なかなかうまくいかなかったですね。2年目からエンジンがかかり始めたのか、どんどんデータが集まるようになって。結局そのなかで一番面白かったのは、声の世界だったんです。村の真ん中で、なぜか一人で大声で叫んでいるじいさんがいるとかね。それがいったい何なんだろう、と最初から心にひっかかっていて、何とかこの現象をつかまえてやりたいと思いました。でもどうやってやったらいいのかわからなくて、いろいろ試行錯誤したんですが、結局最期の2か月で方法を決めて、がーっとデータを取りました。ちょうどボノボの調査隊の人たちがビデオカメラを持ってきていたので、それを借りて大声の様子を撮りました。当時はポータブルのビデオって割合新しくてね。それでデータを持ち帰って、それで博士論文を書きました。
I:ワンバって、このあいだ飛行機をチャーターして行ったところですか?
木村:そうそう。それで、1989年に帰国したあと、ザイールは戦争状態になって危なくて入れなくなったんです。僕は86年に最初に行って、89年に帰ってきて、博士論文書いたらすぐ戻って続きの調査をしようと思っていたんですね。言葉もかなりわかるようになってきてるし、まだいろいろやりたいことあるし。でも行けなくなってしまって。当時はザイールでたくさんの日本人の調査者がいろいろな研究していたのだけど、その人たちがみんな行けなくなってしまって、「難民状態」になってほかの国に流れ出したわけです。僕らは西の方に流れて、最初は隣のコンゴ共和国に行くかという話もあったのですが、コンゴ共和国も危なくなったので、それを飛ばしてその隣のカメルーンに行こうということになりました。結局93年にカメルーンに行って広域調査をすることになったんですね。カメルーンの調査はそれから現在まで続いています。最近5~6年は、コンゴにまた行けるようになったので、カメルーンとコンゴを並行してやっています。
I:木村さんでも現地でなにやっていいかわからないっていう時期があったのですね。
木村:そりゃあ、辛かったですよ。村に入っていても何やっていいかわからなくて、部屋に籠もって持ってきた本を読んで1日過ごしたりして、「あー俺はこんな所まで来て何をやっとるんじゃ」と自己嫌悪に陥るっていう(笑)。そういうことは最初のころは特によくありましたね。
そこで試行錯誤していろいろ考えますよね。そして考えついたことをその場ですぐフィールドノートに書いていく。そのうちのいくつかはかなり後になって結実するけど、いっぱい考えて結実するのは1割か2割か。そういう、心にひっかかる事を心にたくさんでも持っておくっていうのが、すごい大事なんじゃないかな。
われわれの大学院は、「とりあえずフィールド行ってこい」って感じで教育していて、それがいいとか悪いとか議論もあるけれども、僕自身はそうやって放り出されましたね。行く時はあんまりアドバイスしてくれないのに、帰ってきたらけなされるっていうのでやってきた(笑)。まあ、それしかないのかなという気もする。効率は悪いかもしれないけれども。やっぱり実際に行って、いやーな感じ、「俺いったい何やってるんだろう」という感じを、いっぺん乗り越えないとね。フィールドワーカーの、ある種の通過儀礼っていうのかな、通過儀礼って苦しいことをやるわけじゃない。そうしないと新しいステージにいけないっていうところがあるよね。
I:身にしみます。
木村:フィールド行ったら、考えたことを全部フィールドノートに書かないといかんっていう強迫観念みたいなものがありますね。アフリカ行く時はね、関空に行くバスの中から始まって、関空から帰るバスの中で書き終わるんだけど、もう延々とフィールドノートを書き続けますね。夜も枕元にかならず置いて寝ます。
I:今、カメルーンではどんなことをされているのですか。

写真 3
木村:カメルーンの森林には、バカ・ピグミーという狩猟採集民の人たちと、農耕民がいるんですね。ピグミーに会うと、そのインタラクションが農耕民とあまりに違うのに衝撃を受けましたね(写真 3)。それで、カメルーンでは狩猟採集民をやってみようかと。カメルーンに行きはじめてからは就職もしてたし、子どももできたしということで、長期では行けなくなっていたので、対象をインタラクション一本に絞ってやっています。ピグミーと農耕民と日本人という、三者の喋り方や話の内容をデータで比較したりしました。川田順造さん流に言うと、文化の三角測量みたいな。
I:では、ここアフリカ専攻の特徴について、おしえてください。
木村:そうねぇ、フィールドワーク重視っていうのはみんな言ってるけれど。もともと、アフリカ専攻の元であるアフリカセンターは、理学部の生態人類学の伝統をかなり色濃く残していると思うんですね。そういう伝統のなかで、「具体的なデータ」を徹底的に取るっていうのは特徴ではないかと思う。ゼミとかでの討論が基礎になっていると思うんだけど、いい加減なことを言うと、「データはあるのか」とか、「お前本当に見たのか」と。われわれが誇れるのはそういったフィールドのデータに対する、ある種の厳密さっていうのが特徴としてあるんじゃないかなと思っています。
一番基本的なところはね、データと言っても数量的なデータだけではなくて、どこまでフィールドのリアリティを捉えているのかという所なんですね。ゼミの発表でも、数量的なデータを出す人たちばっかりではもちろんないわけです。でも、どんなデータであれ、それは本当にそうなのかという批判は常にあるわけです。「本当」っていうのは何なんだというとなかなか難しいのだけれども、たとえば「○○さんがこれこれのことを言った」ということを記録したとして、それが発話されたコンテキストの中でどういう意味を持つのか、希望なのか愚痴なのか、あるいは調査者へのサービスなのかといったことを、きちんと押さえるっていうことが大切なのね。初心者が陥りやすいのは、ぱっと見たもの、聞いたことをそのまま書いちゃう。最初はしょうがないのだけれども、それをだんだん修正していくということを教える。
I:では、アフリカ専攻をめざしている受験生にひとこと、どんな学生をもとめるかとか、学部時代にこんな経験しておくといいよ、などアドバイスはありますか?
木村:僕自身がね、フィールド始める前は旅行さえ満足にしたことなかったのに、山岳部とかワンゲルとかそういうのばっかりやってきた人のなかに飛び込んだわけです。最初は結構なカルチャーショックはありましたね。そういう人でもやれるんだから、これまでアフリカに行ったことのない人でも熱意と関心さえあれば、なんとかやれる。
I:どういう人が向いているのでしょう。
木村:あんまり神経質ではない人かなぁ。多少なんかあっても、まぁまぁ、何とかなるわ、と「柳に風」的な人がいいんじゃないかと思うんですが。でもそんなんばっかりだと、ちょっと困るかな(笑)。それからやっぱり広い視野を持つ、と言うとちょっと教科書的だけど、いろんなことに関心を持ってフィールドに行ったら面白いと思います。全然自分の研究に役にたたなくていいから、「ああ、おもろい」とね。京大の特徴は「おもろかったらなんでもええんや」っていう所にあるという話があるのですが。僕のときもね、理学部で卒業研究しとってこんなんでいいですかと聞くと、伊谷さんが、「ああ、面白かったらなんでもいいです」って言われて。
難しいですよね。何が面白いのかというのは。だけどたいてい、自分が本当に面白いっていうことだったら他人も一緒に面白いと思ってくれるんじゃないの?という気はします。それが必ずしもすぐに役立つ必要はないから。研究ってそういうものかなって思います。
I:では、木村先生のフィールドの魅力を、教えていただけませんか。

写真 4
木村:コンゴのワンバは首都のキンシャサから直線距離で1000kmくらいあるんですね。コンゴは、戦争が1990年代半ばからずっと続いていて、最近やっと、東部を除いては平和になってきましたが。その後遺症で、交通体系がまったく回復していないんです。昔は途中まで飛行機で行って、そこから車で400km位を走って行けたんですが、今はそれが無理になってしまって、キンシャサからワンバまで高いセスナをチャーターして行ったりしてるんですよ。
でも去年(2011年)、一度船を仕立てて入ってみようということになって、途中のバンダカっていう町から船で行ったんですね。よく見たら二艘をつなぎあわせて双胴船みたいな形になってるでしょ(写真 4)。それに、エンジンを2台つけて。後ろにガソリンつめたドラム缶を20本くらい載せて。それで当初の計画では安く行けるはずだったんです。荷物が大量に積めるし。飛行機で行ったら荷物も限られちゃいますよね。それで多少時間かかってもいいから行こうということでバンダカからワンバまでやってみた。
I:こんなことされてたんですね!すごい船ですね。
木村:まずバンダカで船を仕立てるのが大変だった。僕らが行く前から準備はしてもらってたんですが、それでも出発がどんどん遅れたし、やっと出発できるとなった時もえらいことだったんですよ。ワンバっていうのは上流にあって、バンダカっていうのは下流になるんですね。手漕ぎの船でも流れてくればバンダカまで着けるので、ワンバからいっぱいバンダカに人がきてるのね、バンダカは州都で都市だし。でも帰るのは遡らないといけないからエンジンつきの船じゃないと行けない。手漕ぎでは帰るのは不可能なんですね。そこでみんなこの船に乗って帰りたいわけです。なんとしてでも乗りたいっていうことで、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』みたいな感じでわやわやと来て、乗せてくれ、乗せてくれーって言うわけです。でも、たくさん乗せたらその分、船足が遅くなるし、ガソリンが途中で無くなったらどうなるんだってことで、申し訳ないが、乗せられないと。
いざ出航だというときになって、乗せてくれという人が、勝手にどーんと中に入って座っているわけ。どけーっていって蹴落とした、わけではないけど、そんな感じで降りてもらって。ようやく出港して、よかった、これまでの苦労が報われたと思って涼しい風に吹かれて、ふぅ~って感じでくつろいでたんですね。ところが、何かの用事で、荷物の山を乗り越えて後ろの船頭さんのところへ行ってみるとね、なぜか降ろしたはずの奴が乗ってるわけです。二人くらい見つけて、ああ二人密航者がいた、まぁ、仕方ないなあと、次で寄港したところで降ろそうかと思ったんですよ。ところが結局、密航者7人か8人いてね、そいつらの荷物も小さいながら積んでいるわけです。さてこの密航者をどうするか、降ろすとなるとまた大騒ぎだし、まあしゃあないなということで、その人たちは全員連れて行ったのですが、それでかなり船が重くなって、到着が2日くらい遅れたんじゃないかな。結局、全部で20人くらい乗ってたかな、この船に(写真 5)。

写真 5
I:その人数、すごいですね。この船、木製でしょう?
木村:うん、丸木船です。われわれはここの屋根があるところにベッドを作ってもらってそこに寝てたんですが(写真 6)、その人たちは前や後ろにいて雨が降ったら濡れるし、寝るときはどうしてたんだろ?それやこれやで結局、1週間で行ける予定だったところが12日かかりましたね。

写真 6
I:約倍もかかって。
木村:うん。昼も夜もずーっと走り続けて、そして僕らはほとんどベッドに寝てるわけ。そして上陸したら、地球に戻ってきた宇宙飛行士みたいに足がふらついて、かなり大変だったですね。それなりに面白かったんですけども、こういう美しい風景もみれたし(写真 7)。

写真 7
これとか面白くってこれ、巨大ないかだなんですね(写真 8)。ものすごく長い。百メートルとかある。上に乗っているのはよく見ると家なんです。上に家建てて、いかだの上に街があるみたいな感じで。街ごと流れていってるっていうか。

写真 8
I:これは、流れていって、次に川上にあがるときどうするんですか
木村:バンダカまで流れて行くのだと思うけど、これを見たあたりでは森林で木材を伐採しているんですね(写真 9)。その木材を運ぶのに、こうやっていかだにして流すんです。下流に流れて行くわけだからいつかは着くよね。

写真 9
I:じゃあ、いかだになっているこの木たちも売り物なのですね。
木村:そうそう、木がメインなわけで、上のひとたちは余分というか(笑)。コンゴでも木材伐採がかなりやられるようになってきたんだけど、たぶんトラックとかでは道路状況が悪くて運べないんですね。そこで、河があるし流して運ぶ。伐採道だけはどんどん作られていて、ランドサット衛星画像から合成した地図を見ると、伐採道がたくさん見えるんですよ。
I:その道はだれがつくるのですか?
木村:伐採会社が作っています。熱帯林って、木の根があんまり深くまでいかないので、ブルドーザーでばーんとやるとすぐ倒れちゃう。だからすぐ道が作れる。「コンゴ・フュチュール」っていう会社があって、「コンゴの未来」っていう名前、そこがやってるらしい。
I:すごい名前ですね。
木村:皮肉な名前なんだよね。あんなに森を切って未来はあるのか、っていう感じで。カメルーンの東南部とかも、伐採道がいっぱいあって、いたるところで伐採が進んでいるんですよ。そんなことでなかなか大変な旅ではあったのですが、まあそれなりに面白い旅ではありました。
I:はい、今の話聞いてすごく面白そうだなぁ、やってみたいなあって思いました!
木村:面白いことは面白いけど、つらいこともいっぱいある(笑)。
I:これを読んでいる学生さんのために面白いところを喋ってください。
木村:そりゃ、やっぱり、ある種冒険してるみたいなヒロイックな感じはありますね、こんなことやったの、俺くらいしかいないんじゃないか、みたいなね。確かにアフリカでは日本人ではすくなくとも僕が最初に行ったところもいくつかあるし。
I:やってみたい気もしますが、過酷そうで私にできるんだろうかとも思います。
木村:やってみたら結構できちゃうもんだよ。船旅はなかなか新しい経験でしたね。面白かった。こんどはキサンガニまでバイクで行くっていうのを、来年くらいにやりたいなと思っています。
I:これらのフィールドに最初に訪問した時と、最近訪問したときの違いってどんなことがありますか?
木村:まずカメルーンのフィールドは、いろいろ開発や、国立公園化っていうのが入ってきて、かなり騒々しくなってきています。車やバイクが増えたし、道路がいままでなかった所に通ってたりね。フィールドの村は首都から結構遠いところにあって、最近そこまで行く機会がなくてここ4~5年は行けてないのですが、そこで調査している人たちの話を聞くと非常に騒々しくなってきているらしい。われわれの調査のために建てた小屋も、昔は車も来ない静かな村の中にあったんだけど、そこがすごくうるさくなっていると聞きました。近くにバーが建って、夜中じゅうがんがん音楽流したりね。カメルーンに関してはそんな感じですね。
コンゴに関していうと、逆に悲しいほど違わないみたいなところがあって。戦争があったので経済状態が悪くなったために、後退しちゃったみたいなところもあるわけです。昔はみんな灯油でランプをつけていたけど、今は灯油が手に入らないとかね。2005年に調査を再開したときは、ほんとびっくりした。灯油をちょっと持って行ったのね、自分で使うために。すると、わけてくれー、ってみんなやってくるんですよ。そこで、親しい奴にわけたんだけど、そしたら驚いたことに、5歳とか6歳の子どもは、灯油の光を生まれて初めて見たって言う。ずっとね、灯油さえなかった。昔はそれなりに手に入ったのですが。
それから、昔はコーヒーを売って現金収入があったんだけども、今、道がだめになったからトラック輸送ができなくなって、コーヒーを売ることができないわけです。そうすると現金収入源がなくなってしまった。そこで、どうするかっていったらね、400km離れたキサンガニという都市まで、歩いて行ってものを売るんだよね。歩いて、1週間とか10日とかかかる。夜はどこで寝るのって聞いたら、「森で寝るんや」とね。雨降ったらどうするんや、と聞いたら、「濡れるんや」ってね。歩いてそこまでいって、肉や魚の干したのとか、それから酒とかを売って、その金で塩やら石けんやらをいろいろ買って、また戻るっていうね。ものすごくしんどい。昔はそんなことしてなかったわけですが、今はそういうふうにせざるを得ない状況になっていて、戦争の爪痕っていうのはもう、ひどいですね。調査地では直接戦闘はなくて、死者も出なかったのだけど、そういうところでも、そんな感じになってしまって後退している。
I:私はまだ自分の調査地に行きはじめて5年ほどですけど、それでも「わぁ、変わったな」って思います。幹線道路がきれいになったり、そういうイメージだったので、コンゴのお話をうかがって、ああ、荒廃してしまうところもあるんだなって。
木村:戦争ちゅうのは、いかんですわ。何にせよ、また混乱が起きる、っていうのだけは避けてほしいなぁと思いますね。
コンゴも少しずつ、良くなってきてはいる。2005年の終わりに現地に行ったときは、ほんと市場いっても、ものが無かったけど、最近だんだん充実してきてる。ひとの心も、一時はすごいきつくなっていて、調査を再開したときは、村人たちが集会を開いて、吊し上げみたいなことなってね。俺達のために金を出せ、さもなければ調査はさせないと。そこで、僕のインフォーマントと相談して、全員のためになることだったらお金出してもいいかなあって。橋がぼろぼろで車も通れなかったので、私費で橋を直すことにしたんです。インフォーマントがみんなを仕切ってくれて、木を切り倒して釘を買って橋を直して。計1000ドルで2本、橋が直りました。
I:おお、すごいですね。
木村:まぁ、そういう感じで、以前はとにかく要求がきつかった。最近行ってもそこまでのことはないし、ちょっとずつ人びとの心も和らいできたっていうか。
I:また来たのー、みたいな?
木村:うん、まあね。ほんとコンゴはね、ある種、底がぬけたというか、もう笑うしかないみたいなところはあります。いやー、面白いよ。毒に染まるみたいな感じで、ある種楽しい。悪路を運転するのが楽しくなったり。カメルーンの道はコンゴに比べればはるかにいいわけです。なんかこう、ちょっと物足りんなぁ、みたいなこと言ったら、「木村さんは道が悪い方が好きなんですか」って聞かれたことがあったけど、そういうところもある(笑)。
あと、今ね、研究テーマの一つでもあるんだけど、地元の人たちがローカルNGOを作って、何とか村おこししようと、いろいろ頑張っています。現地にはそういうのがいっぱいあって、一つの村に10個くらいあるんですね。でもいろいろ問題があるんだよね、お金がないってことと、ローカルNGO同士が連携していなくて、ときには対立関係になってしまったり。それは、彼らの社会構造が父系の論理でがっちり固まっているので、村と村との反目も結構強いという背景があるんですね。そういう社会構造っていうのをよく見てみないと、なぜ現象としてそうなるのかをよく理解できない。何とかできないかなと思うんだけど、なかなか根が深いことでもあるし、そう簡単にもいかない問題ですね。
I:研究をつづけていると実践のほうにも眼が…。
木村:それはやっぱりね、最初からそういうつもりはあまりなかったけど、何とかならないかなっていう気持ちにはなりますよね。あの広いコンゴで僕が何かやったからって、それこそ大河の一滴みたいなものだと思うけど、少なくとも僕らがつきあっている連中のためにちょっとくらいは何かできたらいいなっていう気はしますね。そういうことで、今の科研費のテーマはタンパク質の話を取り上げています。森の野生動物が村の近くでは少なくなってしまっていて、ボノボとかも殺したりし始めている。これはアフリカの熱帯林のどこでも問題になっていることなんだけど。そこで家畜を増やせないか、魚類資源はどうか、といった研究を、科研費でやりつつあります。大したことはできないけど、メンバーの松浦直毅さん(静岡県立大学)が、地元のローカルNGOにお金をだして、ブタを飼って増やす試みなどをしています。
I:私も調査地の村の人にお世話になってばかりで、悶々とした思いは常に感じています。
木村:手前味噌の話ですが、そういう、向こうの人たちの現状を知っているのは、われわれだということは思います。それをちゃんと書くことによって世の中に知らせるということで、多少なりと貢献できたらなあと思います。統計資料とか伝聞だけで話をされると信用できないってことはありますよね。ほんとにそこで現地を見てるっていうのは強みだと思います。地道にデータを取ってね。そういうことができるところは我々の特色ですよね。

写真 10