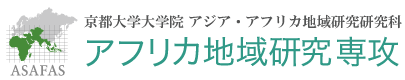*インタビュアー:K
K:それではよろしくお願いします。まず、高橋さんは、どんなきっかけでアフリカに興味を持ったのですか?
高橋:最初にアフリカに興味を持ったのは、小学校低学年のときです。今でいう「アニマルプラネット」や「ダーウィンが来た」のようなテレビ番組を見て、野生動物に興味をもちました。ぼくの子どものころは、あのアニメのディズニーがそうした野生動物を丹念に追った記録映像を作っていました。それを見てアフリカのサバンナに行きたいと思ったんです。それから親が過剰な期待をしたのか、偉人伝をたくさん読まされたんですよ。そのなかで、野口英世の生き方にとっても感動しましたね。彼は、実は梅毒の研究で名を成したのですが、その後進めた黄熱病の研究の道半ばで、現在のガーナで黄熱病自体に罹って亡くなってしまいましたよね。彼の遺体は鉄のお棺に入れられてアメリカに持ち帰られて、研究の対象にされたんですね。そういうのを読んでね、ああ、こういう生き方ってあるんだなって思いました。
少しませていて、小学校6年ぐらいのときには、人種差別とか植民地主義の問題に興味を持つようになっていました。そういう差別や支配は世の中からなくならなければならないと思うようになっていました。時期的には1970年とかね71年とかですね。当時は大学生が大騒ぎして、アメリカ帝国主義打倒とかベトナム戦争反対とか、さかんにデモをやってた時代なのでね。さらに世界地理に特に興味があって、アフリカの地図を見て大きな植民地が残っていることを知りました。ポルトガルの植民地のモザンビークとアンゴラですよね。こういう国ぐには解放しなければいけないと思って、中学1年くらいのときには、夢のひとつですけどね、植民地解放戦線に加わって戦いたいと思っていましたね。今ではおかしな考えと思われるかもしれませんが、でも、たとえば1970年ごろに左翼学生だった人たちのなかには、例えばパレスチナのために戦わなければといって外国に出かけて闘士になっていった人いるでしょ。とするとそんなに異常な考えではなかったかもしれない。
幸いなことに、ぼくが手助けしなくても、アンゴラもモザンビークも1974年ごろには独立しましたので、中学生1年生の身で両地域の植民地解放闘争に身を投じることはありませんでした(笑)。その後中学から高校にかけては、アパルトヘイト、それからアフリカの飢餓の問題に関心を持ちました。で進路を考えるにあたっても大学でアフリカを勉強することを考えないではなかったのですが、1970年代の後半にアフリカの差別問題、貧困問題、開発問題を日本で研究できるところは少なかったし、だんだんと大人になって知恵がついてくると、すぐにアフリカに行って自分がなんでもできるってわけじゃないってことがわかってきたのです。また、当時の京都大学のぼくの中のイメージは、考古学とか霊長類学が強いということで、別に植民地解放闘争とか研究できるわけでもなさそうだったし。だから京都には来なかったんですね。それにほかにもいろんな興味が湧いてきていて、大学に入るころには、アフリカへの興味がワン・オブ・ゼムになってしまっていたかな。それでも、大学に入った後も国際関係、特にアフリカの仕事をしたいと心の片隅では思っていました。それで、アフリカにも、観光旅行ですが、行きました。二十歳のときでした。
K:そのときはどこに行ったんですか?
高橋:観光旅行なので、エジプトとケニアに行きました。ともあれ、ぼくはまだ日本人の学生がめったにアフリカに行かないころに観光に行っているんです。自分でお金貯めてね。ものすごく珍しがられましたね。京大だったらそのころから学部生が行っていたこともあったと思いますが、自分の大学では1学年にひとりもいないくらいだったんじゃないでしょうか。
観光地にしか行ってないんだけど、そのときのケニアのイメージがすごくよかったんです。そのイメージは、独立・自立して、明るく輝かしい未来に向かう国。そのころは、初代大統領のジョモ・ケニヤッタからダニエル・モイに代わって2年しか経っていないころだったな。威厳に満ちたケニヤッタと若々しいモイが並んだ写真がそこら中に貼ってあって、エジプトの古色蒼然としてサービスの悪い感じに比べて、人びとに希望があり、とてもフレンドリーに感じられて、刺激的でしたね。そのイメージがすごく強く心に残りました。
ただ、大学での勉強や学内外の友人との出会いを通じて、主に左翼系の人々が多かったのですが、日本の様々な社会問題にも強い関心を持つようになりました。深くかかわったのは、東京の下町の工場の内外で発生した六価クロム問題です。扱う物質の発がん性などの危険性を知らされずに多くの労働者が働かされていたのですね。そうした弱者のために、社会問題の解決を目指そうと、日本で弁護士になろうと思ったんですけど、経済学部だったんですよね。経済学と法学をどちらも勉強していて、どちらも中途半端に終わった。もしもう少し法律的な頭があって弁護士になっていたら、ここにはいませんでしたね。司法試験に受かろうと粘って大学6年いましたけど、結局試験に受からず、社会問題への志は形にならず・・・家族も随分心配をしていたので、普通の就職をして、外航海運会社の普通のサラリーマンになりました。挫折感をもってですね。
ただ、人間万事塞翁が馬と言いますが、何が幸いするか分かりません。外航海運は国際的な仕事なので、いっぱい英語をつかったんですね。それで、自分って外国人とすぐ仲良くなれるんだなとか、下手な発音の英語でも仕事ってできるんだなと分かって、弁護士の夢は自分でも情けないほど簡単に忘れることになり、いきなり植民地解放闘争に参加するなんて突飛なことも考えなくなり、でも自分は国際協力に関係する仕事もできるのかなって感ずるようになりました。そして、実は、会社に入ってから、ものすごくアフリカに関する本を読むようになっていました。英語のアフリカ史や従属理論の本を大学時代の左翼系の友人たちと読む読書会のようなものもしていました。1980年代は、アフリカは経済危機の時代ですよね。経済成長も停滞して。エチオピアでは大飢饉が起こった年代でもありますし、アパルトヘイトも当然残っていましたから、アフリカでは解決しなきゃいけない問題がたくさんあると思って、ならばアフリカを舞台に活躍する道を模索しようかなという気持ちが再び目覚めてきました。同じころ、勤めていた会社がアフリカに支店を持っていたので、将来赴任させてほしいと書いたら、「そういう変わったことを若いときから言っていると出世できないぞ」と言われました。まあ歴史のある会社はその頃はみんなそうしたものだったかもしれませんが、これは少し将来について真剣に考えなければいけないなと思いました。つまり転身を考え始めたんですね。
結局ですね、26歳か27歳の時に、あと3年間くらい勤めて、それで会社をやめるということを決めました。で、展望もないままやめるわけにもいかないので、国際機関などの仕事を目指すことにしました。親が研究者だったので、親と同じことすることもないだろうと思ってもいました。研究者ってのは辛いものだって、身近で見ていてわかっていたのでね。ほかの人が見なしているみたいに、スマートで安楽な生活でもなく、親が研究者なりの苦しみを抱えているっていうのはわかっていましたから。ただ、他方で、なんとなく家庭の中には、学問することはいいことだって雰囲気があったのも事実ですが。そのことも少し手伝って、会社を辞めて大学院でアフリカの勉強をすることを考えるようになりました。加えて、国際機関を目指したり、国際開発での仕事を目指す皆さんと考えることは同じで、まず欧米の大学院に行こうと。今と違って日本には未だ、国際協力や国際開発を教えるような大学院はありませんでしたし、それらを勉強するのであれば、留学するってのが普通だったのですね。国際機関で活躍したいのなら留学しているほうが有利だともいろいろな人から言われました。国際機関に入っている人は、みんな帰国子女だったり、留学経験者だったりしたんですよ。実はそのとき、もう結婚していたので、会社を辞めて路頭に迷っても困るのと、新婚の妻をつれてアフリカに行くほどの勇気がなかったこともありました。大学時代から付き合いを続けていた周囲の怖い左翼系の友人たちからはいろいろいじめられましたけどね、アフリカの仕事をするのになんで欧米に行くんだよって言われたこともありました。それはそのとおりなんですけど。一つ考えたのは、左翼的な人々は米国をあまり知らずに、帝国主義的だとか言って非難するけれど、本当に米国がどんな国かは知らないで言っているんじゃないかっていう疑念があった。世界を知るなら、米国を知るのも重要だろうと思っていました。それは後から考えると間違っていなかったと思います。ぼくは米国という世界で政治的・経済的に一番力がある国で、世界を見ながらアフリカを考えるっていう勉強を、とにかく2年間しようと思って留学して、そこでアフリカ専攻に入りました。
K:ここからアフリカとかかわり始めるわけですね。
高橋:ぼくが米国に行ってアフリカ専攻に入ったのは1989年なんですよね。このタイミングは重要でした。その米国の大学院で新しい文献をいくつも読まされたのですが、最新のものは皆当然、1980年代という危機と停滞の時代が対象なんですよね。ケニアを訪れて以来ぼくの中にあった70年代ぐらいまでの、自立して開発を目指して国家建設の夢を語って、植民地解放闘争の延長上で、アフリカ人が自らを解放し豊かにしていくっていうものとはまったく違う状況が、実はアフリカの現実なんだっていう論文が多かったわけです。言ってしまえば、欧米などアフリカの外の世界のアフリカ観が地滑りのようにアフロペシミズムに傾いていく時代に、アフリカの研究を開始したわけです。実際アフリカ経済の勉強をしていても、国際機関がとっているデータはみんな暗いもので、結局レポート書いても暗いものにしかならない。そうすると自分自身が非常に暗い気持ちになる。
K:小学校のときからのイメージとはがらっと変わってしまったんですね。
高橋:そういう部分がありますね。それと、ぼくの中にはアフリカ全体が植民地主義・新植民主義の犠牲者とか、人種差別の被害者とか、独立しても、世界の構造の中で従属させられているというイメージもあった。従属理論の本を読んでいたせいかな。米国の大学院で、広く世界で行われているアフリカについての様々な議論を勉強していると、中には独立なんかしない方がよかったと大まじめにいう論者さえいることが分かってきた。それもアフリカの危機、停滞や人権抑圧を憂慮する論者のなかにね。独立自体がよいことだという点では疑ったことがなかったので、考えさせられました。こうした論者が示唆していることは、アフリカは一方的な被害者なのではなくて、独立したアフリカの政治経済それ自体が問題を抱えているということですね。今から考えれば、そうした理解は常識的なものなのですが、その現実を大学院での勉強を通じて突きつけられたわけです。だから非常に暗い気持ちでアフリカのことを勉強していましたね。そこから前向きな気持ちになっていくのは結構大変でした。しかも米国の大学院では要求度は著しく高く、勉強しなければいけない量は半端でないし、会社で使っていた英語なんて学術書や論文読むのにあまり役に立たないので、ものすごく大変だったんです。課される宿題の量がとんでもないんですよね。それを考えると、ASAFASのみなさんにも、もっと勉強してほしいと思いますけど。
K:うわぁ、めちゃくちゃ耳が痛いです。
高橋:ひとつの授業なんか1週間で2冊本を読むわけ。英語ですよ、もちろん。実は、アメリカ人だって、実際読んでいるふりして読んでないやつ多かったけどね。でもそれで2年間勉強したら、いかに多くのことを自分は知らないのかということがわかったし、日本に帰ったらこうやってアフリカのことを勉強した少数の人間のひとりだなと、少し思い上がってますが、考えてしまった。ただ、大学院の勉強を通じてアフリカの複雑さに気づき始めたようにも思います。イギリス人、アメリカ人、そしてアフリカ人の研究者が論じていることとかね、ケニアの作家ングギ・ワ・ジオンゴの自国の政治経済構造の問題性に対する告発とかを読んだりすると、やっぱりぼくが二十歳の時にケニアで見たのは表面的なアフリカのイメージに過ぎないということがわかりましたね。まあ、大学院での勉強は大きな転機でした。
K:大学院を出たあとはどうされたんですか?
高橋:大学院を出て就職するころに、日本のODAの規模が世界一になったんですよね。日本の援助をこれから増やさなきゃいけないというときに、日本のお金はこんなにあるのに、アフリカの専門家が足りないといわれ始めた時代だったんです。大学院を出た時に、いくつか選択肢がありました。ひとつは国連に入ってできる仕事があって、日本政府に紹介してもらえることになってました。自分としては、アパルトヘイトに反対するっていう国連の機関が昔はあったので、そこで働きたかったんです。ところが、幸か不幸か、大学院で勉強している最中の1990年にネルソン・マンデラが釈放されて一気に南アフリカの民主化の流れが始まったんです。これはもう国際社会の出番じゃなくて、南アフリカの人々自身がまず新しい国造りに取り組む時代に入ったんだなって思いましたし、それで家族の問題もあったし、先ほどのようにアフリカの専門家を必要とするというニーズが日本にもあることが分かっていたので、日本に帰って、ODAのシンクタンクみたいなところに入りました。
勤務したのは5年足らずと短かったですが、アフリカの調査にたくさん行かせてもらえてよかったよね。アフリカ以外にも、東南アジアだとミャンマーとブルネイ以外は全部行ったかな。で、ぼくのアフリカへの入り方は、すごくASAFASの他の先生と違って、つまり最初から庶民の生活に入っていくっていうのとは違ってました。いわばフィールドは、まずもってアフリカの役所でした。アフリカの政府機関とかいろいろ回って、いろいろ話を聞き、また交渉などをすると、裏側が見えてきましたね。これもまたつらい経験でしたが、アフリカの当局者たちの責任感のなさ、おしゃべりの空虚さとか、議論の根拠のなさっていうか、組織能力の低さとか、規律の崩壊とか、そういう冷酷な現実を見せつけられました。そうしたことを、例えば東南アジアの政府のあり方と比較できたのはものすごく貴重な経験でした。
最初に3カ月住んだのはザンビアなんですけど、そこで、もちろん身近にいた普通の人びととも、運転手を通訳にしたりしていろいろと話をしました。アフリカの人々との価値観の違いなどもほんの少し感じましたが、そのザンビア人の運転手はものすごくまじめな温かい人で、むしろ彼のように仕事に精を出す普通の人びとに対しては、人間として共感を覚えましたね。対照的に政府機関を回っても多くの人びとはやる気がなく、とても愕然としましたね。
少しザンビアでのあちらの政府との関わりの話をさせてもらいましょう。援助の要請って普通相手の政府が作成して日本大使館に出すんだけど、ぼくが代わりに作ってあげるなんてこともしました。たとえば林業のプロジェクトだったら、あるべき本来のかたちでは、ザンビア政府の林野庁がプロジェクトの内容を策定して、書類を作成し、窓口である先方政府の外務省にもっていって、そこを経由して日本の大使館に要請書が来るわけです。で、実際のザンビア政府の林業プロジェクトの中身はもうすでにできていて、日本の大使館も援助要請がその件についていつかは来ると知っているわけだけど、正式な要請書があがってこない。早くしないと期限が過ぎてしまって、いつ援助案件が始まるか分からなくなってしまう。そこで、ぼくが首都の林野庁の担当部署に行って、なんで要請書を出さないのかって聞いてみたら、交通手段がないって言うんです。首都のルサカにある林野庁本部から百数十キロ離れた町にある専門部署まで行って、プロジェクトの詳細な説明書をとってこないと要請書が仕上がらないんだ、って本庁の職員が言う。半分あきれて、半分はこの国は財政難で予算もないから気の毒だなって思ったし、もう仕方がないのでぼくが自分で、その説明書を取ってきたんです。それで本庁の職員に「説明書とってきてあげたんだから早く要請書を作って、外務省に提出しよう」って言ったら、また交通手段がないって言う。今度は百数十キロの話じゃなくて、同じ首都の中のわずか数百メートル先の外務省までの交通手段がないっていうんですね。もう心の中でキレた。「車がないなら、歩いて持っていけよ!」ってね。でもともあれ、乗りかかった船だから、ぼくがザンビア政府の外務省にもっていって、今度は外務省の日本への要請の担当者に早く日本の大使館に提出してくれと「要請」したわけです。まあ、ザンビア外務省はさすがに、交通手段がないとは言わずに、日本の大使館まで自分でもっていったようですけど。何だか、自分が援助側なのか、受け入れ側なのか分からなくなってしまうような経験でしたが。
しかし、これは、非常に貴重で鮮烈な経験で自分のフィールドワークはこうして首都から始まったっていうか、アフリカ政府の役所から始まった。でも、東南アジアではそんな政府が本来の機能を果たしていないなんて経験ないんですよね。だからこれが、いかにアフリカの政府が脆弱かっていうことの原体験だったかな。こんな国が政府主導で発展することはないんじゃないかって。途上国同士の違いをつぶさにわからないで、支援をしちゃいけないってこともわかったし、そこから経済の研究だけをしているんじゃなくてアフリカの政府のあり方とかも勉強しなくちゃいけないって思うようになりましたね。要するに国家論の研究をしなくちゃいけないって思うようになりました。役人が法律に従って課された仕事を求められる通りに粛々とやっているわけじゃない国も地球上にあるんだっていうのが、非常に重要な経験だったと思いますね。まあ、アフリカの政府の名誉のために言うと、アフリカ政府の職員と長い間付き合ってきて、最近は少し状況が改善したのかな、という気もします。人材も育ってきているし、予算も昔ほどはひっ迫していないかもしれません。若いお役人の中にはとてもモラルや意欲が高いように見受けられる諸君もいますよね。ザンビア政府の職員も含めて。ともあれ、こうした経験は、ずっとその後のぼくの研究の底流にある問題意識につながりました。
もう一つアフリカの政府についての強烈な経験をザンビアでしました。役所に行って、よくあることですが、相手の課長さんが約束の時間に遅れた。それで、課長の秘書でロジ人の女性と四方山話をするなかで、「あなたはいったい誰のことを一番最初に心配するの?」と聞いてみた。日本人の国家公務員だったら、一応建前上は、日本国全体のために働いてるし、日本人は日本人というアイデンティティに基づく公共性の枠組みの下で、社会のこと、国民のことを心配している、少なくともそうした建前にそって、答えるだろうと思います。だけどその前に、日本の国家公務員であっても、家族はもちろん誰より重要ですよね。さて、女性秘書さんの答えでは、まず家族がいちばん大事という点は同じ。でも彼女は、次に親族って言った。ぼくには家族を越えて遠縁の親族のことを心配するって責任感はないし、それはアフリカ人のいいところだなあと思った。で「次に?」って聞いたら、「ロジ人のことが心配」って答えるんですね。日本にも関西人とか九州人とかあったとしても、そういう国民の一部の集団をまとめる絆や公共性っていうのはないですよね。それで最後に心配するのは「他のザンビア人のこと」。彼女も一応国家公務員なんですけどね。まあ彼女は外国人であるぼくに対してわかりやすいようにステレオタイプの話をしてくれたのかなとも、今にして思うけど。これもまた印象に残ることで、課長に数時間待たされたことも含めて鮮烈な体験でした。まあ、その当時(1990年代の初め)に比べると、今では、時間を守るアフリカ人の方々は急速に増えている気はしますね。これもまたザンビア人も含めてね。
その後、ODAのシンクタンクで引き続き働いていたら、ちょうど神戸大学で国際協力研究科ができるという話が聞こえて来ました。ODAの専門家を育てるために高度の教育が必要だという社会の問題意識が形になって、神戸大などに大学院が設置されたわけです。そのときに教員の布陣として、地域研究者はアジアとラテンアメリカの専門家しか置いてなかったんですね。設置の際の神戸大の先生方の頭のなかには、援助の文脈でアフリカが重要だって発想がなかったんですよね。でも93年には第1回のアフリカ開発会議(TICAD)があり、だんだんとアフリカ支援増強の機運が盛り上がってきて、協力隊出身者とかアフリカ帰りが結構多くなってきた。にもかかわらず、多数の学生がアフリカを勉強したいけど、教える人がいないという状態だった。アフリカ経済論の教員を探してるということで、ぼくは経済論だったら経済学そんなにものすごくやったわけじゃないけど、教えられるかなと思って・・・
K:いやいやいやいや!
高橋:一応経済学部出たし、アメリカにいたときもかなり経済の授業とったし、シンクタンクでも経済開発の調査研究をしていたのでアフリカ経済論だったら教えられるかなと思って。で、神戸大に行ったらすごく水が合っちゃったってことですね、アフリカ経済論を教育研究するっていう自分の位置付けに。それと、研究科の性質上、援助の知識も求められましたし、それを教育し、研究することが必要でした。ODAのシンクタンクでの経験はずいぶんと有益でした。結局、アフリカの役に立ちたかったので、援助の研究自体はそれほどしたくなかったんだけど、自分の社会的な使命みたいに感じて援助の研究もしていたってことですが、それが、大学に職をえることにつながったということですかね。その頃には父はすでに亡くなっていて、親と同じ職業に就くことにもこだわりはなくなっていました。
K:えっと、今役に立ちたいけど援助の研究はしたくないと言われましたが・・・?
高橋:その点は少し説明が必要ですね。まず広い意味での支援というのは援助だけではありませんよね。それと、研究者としての本当の関心の芯は、アフリカとはどんなもんかってことにあります、当時も、今もね。そして、援助の研究は、アフリカで起こっていることはどういうことであるかとか、アフリカの国家はどういうもので、アフリカの社会はどういうもので、人びとは国家や社会をどう考えていて、その人びとの暮らしはどういうものなのか、という理解に基づかずにできないと思う。だから援助の研究は、二階建ての家屋の二階というか、いろんなことを積み重ねた後になければいけないと思うのです。
他方で、社会的要請として、アフリカ研究者が非常に少なく、かつ援助のことも分かっていて論じられる研究者はもっと少ないということがあります。実は、この点はわれわれの大きな悩みなんです。現在の国際協力機構(JICA)なんかが研究者に仕事をさせようとすると、結局、ごく少数の人間のところに話が来るわけね。そして、ぼくは、アフリカ援助研究はアフリカ研究の積み重ねられたものの上に乗っかってないといけないと思うんだけど、意外と援助研究をしている人たちは、経済学者を筆頭に、一般化して東南アジアの国家と同じように捉えて、同じメニューで援助をすることを勧めようとする。そして失敗するんです。アフリカ援助研究っていうのは、研究者としては二階建ての二階なんだけど、会社辞めたのもアフリカの役に立ちたいってことでやってきました。そこで、JICAからの頼まれ仕事もできる限り断らずに、頼まれたらまじめにやろうと努めているうちに、日本の援助をできる範囲でよくしたいと考えるようになった。アフリカを知っている人間として、毎年毎年アフリカに行っている人間として、ほかの援助について発言される先生よりは、特に経済学専門の先生よりは、ぼくの方が知っているということで、JICAの援助のあり方も間違えちゃいけないと思ってそれなりに一所懸命に発言をするようになりました。そしたら援助研究の方に時間をとられるようになりました。周囲の学生もそっちの方を期待している面もあるし。何故ぼくにJICAの仕事がそれなりに依頼されてきたかというと、そういう生き方をしてきてしまったからなんですね。たぶんASAFASの方でも、高橋を必要だと思うのはみなさんがやってない援助とか開発の研究を知ってるからってことだったと思うんですけど。ただ、正直に言って自分としてはそっちじゃないことを研究者として、もっともっと深めたいと思っています。
一つ横道にそれるようですが、援助の話を少し敷衍すると、世界の中で西ヨーロッパを中心に1990年代後半から貧困削減というのが強い潮流になっていくんですね。そして2000年のミレニアム宣言に結実するんだけど、それが貧困削減を前面に押し出した開発宣言ですよね。この潮流は正にそうあるべきだと思うし、大事なことで、経済成長とか国全体の経済開発が一番の目標なんじゃなくて、人びとの生活のなかで貧困がなくなっていくのが大事だと、そういう考え方に世界が移っていった。そのとき、ぼくの「言挙げ」の対象ができましたね。
K:その「言挙げ」はどんな論点についてで、相手はどんな立場の人びとですか?
高橋:日本のなかには、さっき言ったミレニアム開発目標に示されたような、開発において貧困削減がいちばん大切だとは考えない人がたくさんいる。アジアの経験などを引きながら、経済成長したおかげで貧困がなくなってきたので、経済成長こそ前提にあってそれが一番大事で、あるいは経済成長こそ国の目標であるとの考え方、産業発展があってこそ国の発展だというような考え方がある。それについて、ぼくはやっぱり順番が逆だと考えていますね。日本や東アジアに広くあるひとつの考え方っていうのは、まず豊かになってから知識をつけて健康になるってものだけど、そういうことじゃない。現実の問題として、人びとが知識をつけて健康になるから産業も発展するだろうし。それは実証的にも根拠のあることだと思います。というわけで、路線論争みたいなのも日本のなかにあるんだけど、そこでぼくは言挙げをしなきゃいけない、と思っています。
「どんな立場が言挙げの対象か」と聞いてもらったので、さらに言わせてください。あえて強調したいところは、たった今言挙げをしたい土俵は、経済成長か、貧困削減かといった次元の論点ではないのです。もっと低い次元というか、援助のそもそも論の話でODAって本来は相手の国のためになくてはいけない。ところがそれを捻じ曲げて日本の国益のためとか日本企業の利益のために援助があるといったことを当たり前のように語る議論が大手を振ってまかり通っている。研究者でも正面からそれに異を唱える人は少ないので、誰かが反対しなければならない。それが当面の言挙げの対象ですかね。難しい話ではなく、あくまでも「援助」という誰かの役に立つという行為の目的は、相手の利益になる、援助であれば相手の困った問題の軽減や解決に貢献するということですよね。それが、今ぼくがいちばん言挙げしなければならないことかな。
さて、繰り返しになりますが、援助の研究も社会的要請からさせられている面があるんだけど、それだけで終わる自分であれば、やはり不満足ですね。貧困削減って言っているからには、貧困の現場とかあるいは貧困の発現形態のひとつである紛争に人びとが動員されるっていうのは、直接、間接に見なきゃいけないだろうと思います。だから自分がアフリカに行ったときには村に行くようにしていたし、あるいは援助を支援し、視察に行くときもやっぱり実施している現場にできるだけ行かせてもらうようにしてきた。プロジェクトをつうじて見ている現場は限られた現場だろうけど、今援助がない村なんて探すほうが難しくなってきているでしょ。アフリカの村々も何かしら外部と繋がっているんですよ。だから援助の現場のフィールドワークってバカにしちゃいけないと思ってますけど。ただ、援助を通じた視点でないフィールドワークも重要なのはもちろんなので、そうしたフィールドワークも人類学者や農村研究の先生にはもちろんかなわないですが、重ねてきたつもりです。ナイロビのキベラをはじめとするスラムにも可能な限り足を運んできました。

K:村のなかで一番印象に残ったフィールドはどこですか? また、村などのフィールドを見るときに何か気を付けていることはありますか?
高橋:まだその村のことを研究し続けていて、神戸のときの教え子とも頻繁に行っているのは、ケニアのエルドレットの近くのキアンバーという村ですね。2007年から08年に起こった「選挙後暴力」という紛争で、三十数名の女性とこどもが逃げ込んだこの村の教会に火がつけられ、焼き殺された。その場所には毎年のように行っています。その地域に調査協力者がいるので学生なんかを送ると泊めてくれる場所があります。紛争のときあんなに凄惨なことにまでエスカレートしたのに、現状は表面的にはいたって平穏です。その落差の背景にあるものは何かってことに関心がある。
「フィールドを見るときに何か気を付けている点」ですが、不勉強を承知で言うと、大昔の民族誌学は国家など関係のないところで生活世界が完結しているっていうかたちの説明が多かったのではないでしょうか。ある村で調査をしていたら、その村のことが全部わかるって感じのパーセプションじゃなかったでしょうか。そうした見方は脱却していかなければいけないでしょう。常に全体、あるいは外の大きな状況とのつながりを念頭に置く必要がある。今日のアフリカの、それぞれの村の現実では、外部世界あるいは国家レベルでの動向、あるいは市場や援助を通じて外から入ってくるモノや情報ってすごく大きな意味をもっていると言って間違いないと思うのです。例えば、いまだに背景はわからないんですが、すぐ前で触れたキアンバーという教会が燃やされた村で、小学校も被害を受けました。それを建て直したのはアメリカの海兵隊の寄付によってだったんです。また、キアンバーの教会の敷地には、それを囲むように柵が作られて公園みたいにしてあるんですが、それは現大統領の寄付で作られた。何より紛争自体が大統領選挙と結びついて起こっているわけで、国家と普通の人びとの運命って端的に言うと繋がっちゃっているわけでしょ。今関心があるのは、その繋がり方ですね。
K:キベラでも村でも国家と普通の人びとの繋がり方にもっとも関心をむけられているんですか?
高橋:そうですね。これをいうと国家を研究している政治学の研究者は単純すぎると反対するかもしれないけど、やっぱり国家は「まとも」である必要があると思うし、じゃあ、今のアフリカの国家が「まとも」かといえばある基準では「まとも」ではないわけですよね。これについては、われわれの価値基準というものがあってそれで測っている訳だから、アフリカの歴史の浅い国家が「まとも」でないのは当たり前かもしれない。他方で、どういう社会のあり方がアフリカの人びとのためにあるべきものなのか、そして持続的なのか、ということは非常に難しい問題ですよね。もしかして、先進国の基準から見たまともな国家の存在しない無政府のアフリカ社会というものこそ、アフリカの人びとのためにはあるべきものなのかもしれない。
しかし、恐らく、社会科学の常識にとらわれているかもしれないけれど、具体的なかたちはいろいろあり得るとしても、国民の社会への包摂・統合を成し遂げ、それを支え続け、国民の利益を公平に図っていくような国家というものはアフリカの諸社会にも必要だと思うんですよ。もちろん、一方で、それはなんらかの形でアフリカ化される、言い換えればアフリカの具体的な文化や環境などの状況に適合したものに陶冶され直してていく必要もあるとは思うんだけど。よく指摘されるように、アフリカの国家建設で困難な課題なのはアフリカの多くの国で民族が多様だってことですよね。しかし、現在ある国家を民族ごとに分割するという議論は決して生産的ではないでしょう。
もしかしたら国家そのものが決定的な要素ではないかもしれないけれども、でもアフリカの国家はやはり変わっていかなければならないだろうと思います。アフリカでも、国によっては、何千万人あるいは1億人以上の人びとがいるわけですが、その人びとの集合全体の運命をみる大きな組織ってものは何かなければいけなくて、それがどういうものであるべきかってことにはずっと関心があります。
さて、社会の機能を支えるものとして、国家に対して経済学者の頭のなかで対置されるのは市場ですね。経済を少しでも勉強しようとする人間がちゃんと知らないといけないことは、市場はいいこともするけど悪いこともするってことです。人びとは市場によっていろんなものを手に入れることができますよね。あるいはモノやサービスを得ることで生活が多様になりますよね。このこと自体は、人によって意見が違うけど、ぼくは悪いことじゃないと思います。最低生活水準でいつ飢えて死ぬかわからないよりは、市場でいろんなものを手に入れられて、いざとなれば必要な生活物資を買えるのはいいことだと思います。もちろん、逆にそのために代金の元手を市場なりで稼がなきゃいけないけどね。けれども市場経済というのは、ほっておくと暴走します。例えば、「強欲資本主義」って言葉ありますね。強欲化する、というのは噛み砕いて言えば、人びとの利益になるべき市場の私的な自己利益追求の一面だけが極端に突出して、広く人びとを傷つけるような状況が生まれるということだと言えます。これこそ、現在の世界で起こっている市場の巨大な失敗の例ですね。今、欧米で起こっている社会の分断や排外主義は、ある意味市場の強欲化に対する反発の、かなりこわばった形での発露だとも言えなくもないでしょう。市場の強欲化の下では経済が人間のためのものではなくなるわけですね。
これを規制することが必要で、じゃあアフリカでの状況はどうなっているのかっていうのが、今の重要な関心事。そうした点では政府はあまり力がない。全体としても人びとの役に立っているのか必ずしもわからないし、下手をすると権力を握った人間が自ら強欲に走って、直接的、間接的に自国の国民を傷つけている場合もあるわけですよね。そういう国家の下では、市場がいろいろ悪さをしても政府が人びとを守れない、規制できないんですよね。特に、開発の世界でいうセイフティネット、市場の変動に対して人びとの暮らしを守る仕組みを政府が提供しているわけではないことが多い。国家は人びとにサービスを提供していますね。ただ、そのサービスは一方的で、たとえば道路を作るとか学校を作るとか診療所を作るとかは援助を用いながらしているかもしれない。だけど、例えば、失業したときにちゃんと失業保険を供与しているか。先進国のことを考えれば、企業が放り出してしまった人びとを救う制度が曲がりなりにもあるわけです。でもそんなもんアフリカにはほとんどないわけでしょ。じゃあ今どうしているのか。みんな自分たち自身で助け合いをしているわけだよね。だから自分たちでセイフティネットを作ることがとっても大事になっていますよね。今切に思っていることの一つは、ある意味で、国家や市場が自分たちの生活のなかに侵食してくるのを、自分たちで飼いならそうとしているところを、ASAFASに来たからには、自分の研究をつうじて学び、また、みなさんの研究をつうじて教えてもらいたいということです。
もう一つ重要なことですが、アフリカの国家は普通の人びとに対して、どういう関係にあるかということを多面的に捉える必要がありますね。規制や保護をするという面では無力な国家であると言われているけれど、じゃあなんで、普通の人びとが国家権力の行き先をめぐって選挙であんなに血眼になるのかっている問題は考えなければならない。例えば、ぼくがいちばん頻繁に行っているケニアという国は政府が人びとの運命を左右してきたってところがたしかにある。そうじゃないと、「選挙後暴力」の場合がそうであったように、選挙のときにみんながあんなに扇動されて殺し合いになることはないんですよ。
ケニアの独立から間もない時期にさかのぼると、初代のジョモ・ケニヤッタ大統領の政権の下で入植政策によって彼の民族であるキクユ人のかなり多数の人々が、異なる民族であるカレンジン人やマサイ人が住んでいた地域に土地を与えられたんですね。それが先ほども述べた「選挙後暴力」に至る民族対立の始まりの一つになっている。じゃあなぜジョモ・ケニヤッタの政府がキクユ人のための入植政策をやったか。それは強権で腐敗にまみれたケニアの政治の創始者のように見えるジョモ・ケニヤッタ大統領でも、自民族の大衆の要求をすべて無視しては政権を維持できなかったということでしょうね。つまり、アフリカの国家も、普通の人びとから遊離しているようで、やっぱり普通の人びとなしには存在できないということなのだと思います。詳しくは省略しますが、ケニヤッタにとって、植民地時代の末期に起こったマウマウ戦争の原因となったキクユの人びとの土地への渇望って無視できなかったと思います。そうでないと、入植政策によって自分の取り巻きでもなんでもない人に土地を与える政策をとったことが説明できません。
そして、政府には、援助の力は借りているかもしれないけれど、学校を作り、道路を作る力はあるわけで、それを通じて人びと、あるいは民族の間に格差をつくり出すこともできる。意識するかしないかは別としてね。だから少なくともケニアでは、人びとは、権力が対立する民族のものとなって、自分たちが結果として差別され、疎外されることを恐ろしいと考えています。つまり、ケニアでも普通の人びとにとって、権力には意味があるわけですよ。ぼくの調査を通じて旧紛争地の人びとに聞いたところ、大統領は部族主義者ではない人、つまり自分の民族にひいきをしない人がいいって大半が答えるんですよね。アフリカの普通の人びと自身が、国家や権力者は公平であるべきだ、というしっかりした考えを持っている。旧紛争地でもそうなのだから、骨の髄まで部族主義者の人を見つけるのは、実はむずかしいのですね。一方で、自分の民族が差別されることを恐れて、敵対する民族の大統領の登場には反対する、あるいはいい気はしない。
そういう人びとの複雑な心境って、今の変わりつつあるアフリカの姿を現していて、言い換えれば、みんな民主主義の理想みたいなのある程度わかってるし、心のどこかで自分の国にも実現したらいいなと思っているし。で、政治、経済、行政のリーダーだって同じように考えている人がいるでしょう。たとえ、100%民主主義を信じていなくとも。そこで、アフリカ国家の本質は家産制だとかパトロン・クライアント関係だとか言っているだけだと、それは一面的な理解に過ぎないですよね。そこを本当に、今のアフリカがどうなっているのを理解したい。そこでぼくは、フィールドだけで、村からだけの視点で理解するんじゃなくて国家全体を理解したい。若い皆さんも、村に視点を当てるのは、それはそれでよいのですが、他方で広いコンテキストのなかで、自らの研究対象をうまく捉えてもらいたいと思う。国際社会とのつながりに目を向けられた研究もありますけど、もっと村における国家や市場との関係にも目を向けられてもいいのかなと思います。
K:それでは最後にASAFASでのこれからの抱負をお願いします。
高橋:定年まであと8年足らずなんですけど、ここの生活をエンジョイしたいと思っていますし、アフリカ支援や援助に興味のある人とは大いに話をしたい。日本がアフリカのために援助をするっていうのはまだまだ必要だし、先ほど言ったようにむしろベクトルは逆に動いていますからね。日本の国益のために援助する、アフリカの方が日本に役立つと。順番がそこも逆になっている気がするので、そうじゃない、アフリカの援助をするんだったらアフリカのためになることをまず考えようって思います。でもそれは人類学者の先生方に諭されるように、日本がアフリカのためにって一方的に、自分勝手に考えることはもちろんできないわけだから。対話をしなきゃいけないですよね。普通の人びととの間で、その対話を一番できるのはASAFASの諸君だと思うので、ぼくはそういうお手伝いをしたいと思います。アフリカそのものの研究をする人と開発や援助の研究をする人、あるいは同じ個人のなかにもそれらが併存している人もいるかもしれないけど。開発研究とアフリカ研究とね。それらの二つもまた、相互に対話することが大切ではないかと思っています。せっかくASAFASに来たので、自分の研究を進めるとともに、みなさんともそれらのことをめぐって対話していきたいと思っています。