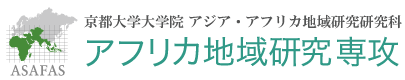教員インタビュー
高田 明
専門:人類学、アフリカ地域研究
*インタビュアー:A (インタビュー実施日:2020年12月)
A:高田さんの現在の研究の内容及びこれからの研究の方向性についてお聞かせください。
高田:大学院生時代から、色々なテーマについて研究してきたのですが、最初から一番長くやっているのは子どもと養育者の相互行為、つまり乳幼児の子育てについての研究です。そこから色々な研究テーマが浮かんできて、手を広げてきています。たとえば、現地の人が環境をどうやって見ているか、サンが砂漠の中でどのように道案内をしているか、サンの中の色々なグループのエスニック・アイデンティティがどのように変わってきているか、さらに最近は乳幼児よりもう少し年齢の大きい子どもの学校、家庭やコミュニティにおける広い意味での教育、宣教団や国家規模で導入された教育システムについても研究しています。
A:高田さんは狩猟採集民サンの子どもの研究をされていますが、どうしてこうした研究をされているのですか?
高田:最初は、どちらかというと子どもの研究をしようと思って、ASAFASの前身だった大学院、当時はまだ人間・環境学研究科の一部でしたけど、に入りました。その当時から、特にアフリカの子どもの研究の中では、狩猟採集社会の研究がわりと盛んだったんですね。僕自身も現地に行って、参与観察をしたい、生活の中で子育てを直接見たいと思った時に、狩猟採集社会の子育てが色々なトピックとの関連で注目されているのを知って、そういう研究を始めました。
A:高田さんは相互行為分析や会話分析など詳細な分析をされていますが、その手法を選んだのはどうしてですか?
高田:私はどちらかというと社会全体を全部見渡すような大きな研究よりも、細部にこだわって、じーっと観察するような研究が好きなんですね。もしかしたら昔昆虫少年だったというのも関係するのかもしれません。
A:へえ。そうなんですね。
高田:はい。あの、なんというか、元気に動いているものを見ること、それがどうしてそのようになっているのかなあというのをじーっと観察するのが好きなんです。相互行為分析や会話分析はそういう関心をある程度満たしてくれます。そういえば、ここにあるイラストも根っこは同じで、じーっと見ながら丁寧に細部がどうなっているのか考えるのが好きというのがあります。
A:このイラストは手前の子どもが話しかけているようですが、何をしているところなのでしょうか(写真1)?

高田:これはね、これはナミビアのEという村の幼稚園で子どもたちが遊んでいるところの写真が元になっています。下の段の2人は、そこに住んでいる農牧民のオバンボの子ども達。手前の男の子は他の子と何かやりとりを始めたそうな感じです。その隣の女の子はそれをじーっとみて、いったい何が起こっているのかなあと思っていそう。後ろ3人の子は皆サンの子どもたちなんですけど、前の2人の子どもや写真を撮っている僕の方を興味深そうに見ていました。それぞれよく見てみると、関心を持っているところや視点が違うのが面白いと思ってイラスト化しました。
A:サンの子どもとオバンボの子どもは一緒に遊ぶこともあるのですか?
高田:そうなんです。この幼稚園そのものが、その地域の中でのサンに対する偏見を無くそうというUNESCOのプロジェクトの一環で作られました。子どもたちはそんな大きな目的は意識していなかったと思いますけど、幼稚園が作られたことで一緒に遊ぶ機会が増えました。僕もその時にフィールドにいたので、それを実感しながら撮ったワンシーンです。
A:高田さんは絵を描くのがお好きなんですか?
高田:そうですね。フィールドにいる時も研究に煮詰まったらずっと絵を描いてますね。あと絵を描いてきたら子どもが寄って来たり、描いてあげたら喜んだり、泣いたりして子どもとコミュニケーションをとる契機になるというのもあります。あと日本に帰ってきてからも、ときどき描いてますね。フィールドワークってデータをとっていると結構楽しいんだけど、その後の分析や執筆でモチベーションが上がらない時ってAさんもない?そういう時に写真を見てイラストを描いていたりすると、当時のことを思い出したり、意外とその場面では気づかなかったことに気づいたりしていいかなと思ってやっています。
A:私も絵を描くのが好きです。画材はどのような物を使っていますか?フィールドに色鉛筆とか持って行ったりしますか?
高田:フィールドで描くのが主なので、なるだけコンパクトにしています。実際はフィールドノートにボールペンで描くことが多くですね。もう少し時間をとれるときはスケッチブックと色鉛筆を使います。
A:高田さんはたくさん論文を書かれていますが、その毎回のトピックはどのように選んでいるのですか?
高田:そうだねえ、Aさんは今大学院生だよね。その頃のことを思い出すと、最初は割と漠然とした全体を覆うような関心があった気がします。それが実際に先行研究とかを見ながら論文を書き始めると、だんだんぼんやりとしていた問題意識が具体的に絞られてくる気がします。ただその一つ一つの論文を書いていくと、そこでフォーカスが絞られたが故にまだ解決できなかった問題が必ずいっぱい残ってきます。そうすると、一つの論文を書くと、次にそれが2つぐらいのテーマに分かれて、その次にそのテーマをやっていると、それがまた4つぐらいの解決していないテーマに分かれていきます。これを僕は勝手に「ポケットの中のビスケット理論」と呼んでいるんですけど...。
A:面白い表現ですね。
高田:そういう歌があるよね。ポケットを叩くとビスケットが2つという歌詞ですけど、あれはビスケットが粉々になって消えていくのではなく、元の大きさに戻って増えていくという歌だったと思います。論文もそういうところがあって、書くたびにテーマが増えていくので一生終わらんなということをよく思っています。
A:高田さんはアフリカ専攻の全体ゼミで、学生の研究テーマが様々であるにもかかわらず、建設的、理論的なアドバイスをよくされておられ、幅広い分野に精通されているなと感じています。日ごろから、何か心がけていることなどありますか?
高田:そういう印象を持っていただけると嬉しいです。たぶん僕自身の大学院生からこれまでの経歴を反映しているのかなと思います。僕は自分でテーマを探すのが好きで、逆に言うと上からテーマを与えられたらやる気があまり起きないところがありみたいです。それで、関心を持ったことを自分で色々勉強して深めるというのをずっとやってきたように思います。それもあって、自分が関わっている学生さんにはできるだけ自分で考えてテーマを考えて選ぶということをして欲しいと思っています。ですから、できるだけ学生さんの関心に自分の興味を寄せて考えるということを心がけているところはありますね。
A:あと高田さんは海外の研究者と交流が多いように感じます。国によって、研究者の研究の特徴があるように感じることはありますか?
高田:この写真の隣にいる先生は、僕が大学院生時代からすごくお世話になって、残念ながら最近亡くなられたCharles GoodwinさんというUCLAの相互行為論の大家、この後ろにいる方はJürgen Streeckさんという相互行為論やジェスチャー研究の先生です。さっき言ったこれまでの経緯と関連しているかもしれないんですけど、僕は自分がいる研究室の方針に従って研究をやるという感じではなくて、自分で関心を見つけて研究をしてきたので、自分が面白いと思った研究分野の専門の先生となるだけ積極的に交流をとるようにしてきました(写真2)。そうすると、国も分野も色々なところの人と関わるということが増えてきました。最初は点で色々なところに行っていたのが、だんだんと網の目のように繋がってきて、幅広い研究者のネットワークに関わるようになったという印象を持っています。

A:国によって研究の特徴や違いはありますか?
高田:僕がこれまで割と深くかかわった国は、日本、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリスくらいですかね。フィールドワークに基づく研究はそのフィールドと深く関わっているというのもあるし、一期一会の参与観察に基づいているということも影響していると思うんですけど、研究グループによって研究の特徴に違いがあるように思います。
うまくまとめるのは大変ですけど、まずアメリカの特徴というと、研究者の人口が多く、研究に関する大きな予算のついた大きなプロジェクトが多い印象を持っています。それぞれのプロジェクトについてその中心メンバーの理論的な関心が強く出る傾向があって、かつ大勢の研究者がプロジェクト単位で動くことが多いので、理論的な関心がどんどんと変わっていく印象を受けます。そうすると、短期間に大勢の研究者がすごく集中してわっとその領域について研究をやって、ある程度時間が経つとまた違う領域をみんなでわっとやるイメージですね。幅広い分野でそのような傾向があるように思いますが、僕の専門の人類学についてもそんな気がします。さらにアメリカでは日本とは違って、それが大学の制度にも反映されています。大きなプロジェクトが終わったらそれが独立した学科になったり、そうした関心を持ったテーマで大学院生がずっと勉強してその専門家になったりということが頻繁に起こるので、研究分野全体としてトレンドがどんどん変わっていき、大学の組織もそれに合わせて柔軟に変化していくところが強みかなと思います。いっぽう、日本は学部や学科といった大きな枠そのものは変えないで、その中でその時々のプロジェクトをやるという印象があるので、なんかこう家を守るみたいな感じで、根っこのところは変わりにくいですね。ただ、そのおかげでアフ研だったら初期の探検マインドみたいなのが長く続くとか、一つの調査地に何十年も関わり続けるといったアメリカでは生じ難いよさもありますね。お国柄を反映しているようにも思えますが、どちらの仕組みにも長所・短所があると思います。
あと、僕の分野だったら南アフリカもすごく研究が盛んです。南アフリカには、僕が行っている調査地、ナミビアとかボツワナの調査をしている優れた研究者がたくさんいます。こうした研究では、研究者が生活している土地がフィールドに近いだけあって、人類学でもかなり地域の政治に対しての関心が強いとか、その社会をよりよくしていこうとか、より自分達の問題として関わっている感じがします。
A:ヨーロッパはどうですか?
高田:そうですね、僕が一昨年長期滞在したドイツは、日本と似ている特徴としては現地での地道なデータ収集みたいなのを重んじるという印象を持っています。これは、アメリカと比べた時に、どちらかというと日本と似ている特徴だなと感じました。その一方で、日本よりは頑固に理論的な関心を持ち続けている人がかなりいて、データをじっくり取る人と理論のことをじっくり考えている人が共存している社会だなと感じました。
A:私も色々な海外の研究者と交流して知見を広めたいなと思いました。
高田:ぜひ交流してください。フランスの研究者にはフィールドで会うことがあるかな?
A:フィールドで出会うことは今までにはあまりなかったので、これから楽しみです。
高田:そうですね。フィールドで会うのと、学会で会うのと、あるいは欧米の研究室に出かけて行って会うのとでは、研究者同士の関係もずいぶん変わってくるように思います。一番楽しいのはフィールドで出会うことかもしれないですね。
A:次にフィールドについて伺いたいと思います。初めてアフリカで調査されたときのことを伺います。いつ、どこへ行かれて、印象に残っていることは何ですか?
高田:はい、一番初めにアフリカに行ったのは1997年で、南部アフリカを回りました。その時の写真がこれですね(写真3)。

A:高田さんですか?
高田:はい、おじさんも若い頃痩せていた頃がありましたよという感じですね(笑)。
A:これは何歳くらいの時なんですか?
高田:これは25歳から26歳になる、その誕生日をまたぐ頃だと思います。
A:私と同い年です。
高田:そうですね。この時はカラハリ砂漠を訪れました。論文とか先生や先輩の文章では知っていたんですけど、実際に行ってみると想像を超えることがいっぱいありました。そうですね、例えばこれ結構厚めのジャケットを着てますね。カラハリはもう朝がすごく寒くて、特に6月7月なんかはマイナスになったりするんです。だからすごく厚着をしています。でも、日中どんどんどんどん気温が上がってきて、真冬でも日なただと40度ちょっと手前ぐらいまで行きます。それで、一枚ずつ上着を脱いでいくみたいなことを毎日毎日繰り返すんです。これはたぶんもう暖かくなって昼寝をしているところだと思います。そんな気候の変化も、最初行く前はほとんどイメージができていませんでした。最初一年くらい行く予定で行ったんで、フィールドワークって毎日何するんやろう、一年間も毎日何してたらいいんやろうと思ってました。でも、朝ご飯、昼ご飯、夕ご飯の準備を自分でしてたら、その準備だけで合計5時間くらいかかるんですね。それから、その間に人について色々なところをまわっていると、結構熱いし、砂漠の砂は重たいので、あっという間に時間が過ぎたなという印象がありますね。あと人がすごく優しかったです。色々なフィールドについて書いた文章は読んでいたんですけど、結構フィールドによって印象は違いました。僕が最初ボツワナのフィールドに行って感じた印象は、すごい優しくて受け入れてくれる人達だなというものです。時間とともにわかってきたことは増えていますが、その大きな印象は今も変わらないですね。
A:この写真は誰に撮ってもらったんですか?
高田:これはたぶん現地の人ちゃうかな。僕が寝てたから自分では撮ってないですね。
A:砂漠という調査地ならではのエピソードはありますか?
高田:さっき言った気温の変化なんかも大きな特徴なんですけど、フィールドワークを進めていくにつれて、日本とはずいぶん違う環境の中で、あちらの人達がどんな風に生活しているかというのが調査としても、実生活としてもだんだん分かってきました。中でもやっぱり、ずっと雨が降らないということは日本で想像していた以上に色々な影響があるなあっていうのを実感しました。例えば屋根がちゃんとしていない家でも全然普通に生活していて不便がなかったし、あと洗濯物がすごく早く乾くんですね。僕は日本にいたらじめじめしているのが苦手なんですけど、向こうに行くと洗濯物がものすごく乾くし、快適だなと思った印象がすごく残っています。砂漠なのでお風呂は水がなくて入れないんですけど。年間降水量でいうとわずか400~600㎜くらいのところなんですけど、まとめて雨が降る時があります。そうするとこの写真みたいに大きな水たまりが砂漠の中にできるんですね(写真4)。するとあっちの子ども達はすごく喜んで、あっという間に裸になって水遊びをしたり、自由に遊んだりして楽しそうでした。あと雨が降ると大きなカエルがでてきて、それが晩御飯のおかずになっていました。あとイモムシ。色々な種類の蛾の幼虫が食用になっているんですけど、雨期にはそうしたイモムシが大発生してました。乾燥地だけに、少しの雨で見られる植物とか動物がどんどん変わって、それに伴って人の生活もどんどん変わるみたいなことがすごく印象に残っていますね。

A:この写真の後ろにいるのはウシですか?
高田:そうですね。
A:こんな感じで自由に放牧しているんですか?
高田:耳に一応タグがついているので持ち主はちゃんと把握していると思うんですけど…これは政府から割と最近に配られたウシなんです。ヤギはクラールというヤギ囲いに入れられるんですけど、ウシはかなり自由にしていて、夜になってもほったらかしの時もありました。牧畜民からしたらびっくりするぐらい自由にウシを放している感じはありましたね。このウシは結構太っていますね。雨季だからかな。
A:ナミビアの調査地はご自分で開拓されたと伺っていますが、どのように開拓し、現地の人に受け入れてもらったのですか?
高田:そうですね、最初はボツワナに予備調査に行ったんですけど、当時ボツワナのグイとガナの移住が起こって調査許可がなかなかおりなくて、別の調査地を探してナミビアに行きました。日本のサン研究者はほとんどがずっとボツワナを調査地にしてきたので、その以外の調査地はあまり知られていなかったんですね。最初は指導教員だった田中二郎先生と一緒にナミビアの首都に行って、ナミビアで調査をしているアメリカ人の研究者とか、当時ナミビアで大きなプロジェクトを始めていたユネスコのアメリカ人やドイツ人やナミビア人のスタッフに話を聞きました。フィールドに行く途中で田中先生は帰られたので、その後は色々聞いた情報を基に自分で調査地を探しに行きました。当時、まだ今ほど外国に行く経験はなかったですし、海外の研究者と交流するというのもまだ少なかったので、色々な土地の名前や人の名前を聞いて、手探りでそこに行って、現地の行政官と話をしたり、村の近くに行ったら村長さんと話をしたり、すごく新鮮だった記憶がありますね。その前の年にもボツワナで調査地入りはしていたんですけど、その時は日本人の調査チームが何十年も調査をしてきたところだったのであまり考えずに進めていたところが、一からステップをおって調査地を探すという経験をしたことで、先輩達の苦労が分かるというのもあるし、全然違う視点で地域社会とかかわることになるので楽しかった気がします。これなんかは調査地を探しに行く過程で撮った写真だと思うんですけど、写っている人達もナミビアのサンの人達なんですね(写真5)。ボツワナの調査地のサンの人達は、色々なサンのグループの中でも比較的最近まで狩猟採集をかなり活発にやってきたグループなんですけど、ナミビアの調査地のサンの人達はもう数世紀に渡って周りの農牧民と深く関わってきています。あとこの地域は、宣教団の影響とか、ナミビアが南アからの独立を目指した解放運動とも関わりが深いところです。そうした社会的状況の違いは知識では知っていたんですけど、実際フィールドの近くに行くと、改めて新鮮に感じることが多かったですね。これ、真ん中に農牧民の奥さんがいて、その家で雇われたサンの人達がトウジンビエやソルガムの脱粒をしているところなんです。サンの人達がこうやって集まって農牧民のもとで仕事をしているという姿を目の当たりにして、ずいぶん違うところに来たなあと思いました。こういう光景を見ることで、サンのイメージについても深く考え始めたような記憶がありますね。サンの調査をするためにはもちろん行政機関とか研究者とのコンタクトも大事なんですけど、まずは土地の人に話を聞いて、農牧民の村長さんに話をしないと何も前に進まないとか、調査地に入って行く過程でだんだんわかってきました。そういうのも事前情報があまりなかったので、手探りでそういうことを聞いたり見たりして進めていったというのが大学院生の時の大きな経験になりましたね。

A:気候や食事、生活上の苦労はありましたか?
高田:さっき言ったように、慣れない気候なんかに最初は戸惑ったんですけど、それ自体は若かったこともあってそんなには気にならなくてすぐに慣れていきました。あと食べ物もそんなに好き嫌いがないほうだったので、苦労したという記憶はあまりないです。
A:どんな食べ物なんですか?
高田:ボツワナやナミビアの調査では長距離の移動が必要なので、日本人の研究者は長年車を使った調査をしてきました。僕自身も自分で車を運転していたので、町で買っていける食材(野菜、缶詰、トウモロコシの粉とか)と現地でとれる野生の動植物を組み合わせて料理をしていました。基本は自分のテントを張って、そこで調査助手をしてもらう人に毎日来てもらって一緒にご飯を作るという形です。この写真は当時の僕と同じくらいの年で調査助手をしてくれた人です。頭の回転の速い、何でもできる人で、かつ年も近いので、僕にとっては親友のような感じです。彼と一緒に生活しながら、彼の知り合いなんかを通じてだんだんと現地の人達の関係に入っていくような感じですかね(写真6)。あと僕は子育ての調査をしていたので彼、ニホというんですけど、ニホの赤ちゃんを一緒に見させてもらったり、家族に赤ちゃんについて話してもらったりということをしていて楽しかったです。まあ苦労したと言えば、結構ね、皆よく飲むんです、お酒を(笑)。これ、同じニホなんですけど…(写真7)


A:同じ人なんですか?!(笑)
高田:同じ人です。暗くなってくると、多くの人がコカショップと言う、地元のバーみたいなところで時間を過ごします。僕は、コカショップの中でも聞き取り調査をしていました。今だったら絶対できないと思いますけど、一緒にお酒を飲んでずっと時間を過ごしながら何か聞くということをやってました。それが毎日続いていたのでそれは結構しんどいなということもありました。
A:フィールドに行く面白さは何ですか?
高田:今の話にも繋がるかもしれないんですけど、フィールドワークはいちおう大学院の研究なんだけど、自分の生活と切り離せないというか、生活の一部になってくるようなものですよね。だから研究テーマの選び方にしても、研究データとして色々なことを調べていくにしても、その人の考え方とか生活への関わり方がすごく影響すると思うんですね。それは積極的なワーカホリックのようなところがあって、一面では苦労があるかもしれないんですけど、その反面それがすごく面白いところだと思います。全然遠い世界で生活をしていく過程で、自分が不思議に思っていたこととか、昔から関心を持っていたこととかについて考える鍵に出会ったり、答えの端っこみたいなのを拾ったりみたいなことが色々な場面で起こる気がします。それが必ずしも論文にはならないんだけどずっとそれについて関心を持っていることで、研究だけじゃなくて生活も豊かになっていく気がする。そういうところが面白さかな。とはいえ、途中で考えられなくなったり行き詰ったりすることは多いんですけどね。この写真は…たぶんAさんもネコが好きだったと思うんですけど、フィールドで僕が飼っていたネコです。野良猫だったんですけど、家にすみついたので僕が飼っていることにしてました。オルモショという“左手”という名前のネコなんです。疲れたときは昼寝したり、飼ってたネコと遊んだり…このネコは活発で、夜はテントのフライの上を寝床にしていたんですけど、僕が焚火に出ている時はそこに出てきて集まってくるカマキリをものすごいスピードで捕まえて食べていました。中々賢いなと思ってました(写真8)。僕はサンの研究をしに行ったはずなんですけど、フィールドではネコとかヤギとか色々な動物を飼っていて、そのネコのフィールドノートとかヤギのフィールドノートとか論文になってはないんですけど書いていたりして、そんなことも楽しい思い出ですね。

A:見てみたいです(笑)
高田:僕がアフ研に入る前にいたところが心理学の実験室実験をやるところだったんですけど、どうもそれが性に合わなかったんですね。それで、もっと自由に行動している人を見たいと思ってアフ研に来ました。同じような感じで、動物も野生の環境で生きているのをそのままじっと見るのが好きですね。そういう思いも満たしてくれるようなところがフィールドワークの面白い点の一つかなと思っています。
A:ここに書かれている文字「水が沸騰するまでに鍋に蓋をしたら次回獲物がとれない」が気になります。
高田:ああこれ、ご飯作ってた時に調査を手伝ってくれた人が言ってくれた言葉で、何かの野生動物か家畜を晩御飯にした時だと思います。これはナミビアでのフィールドノートです。彼らは当時もうあんまり狩猟は活発にやってなかったんですけど、ここで書かれているみたいな狩猟に関わる色々な慣習とか決まり事がありました。一見するとポスト狩猟採集民みたいに見えるんだけど、実際に関わっていくと狩猟採集に関わる習慣や行動のパターンをずいぶんと実践しているなあという印象がありましたね。でもこれ、ちょっと書いた後、ご飯の準備の間、ずっとこのネコ書いてたんだけどね(笑)。普通のフィールドノートにボールペンで描いているんですけど、ノートの文字を書いていた時より、絵を描いていた時の方が思い出しやすいですね。
A:スケッチしながらフィールドノートとるといいですね。記憶にも残って。
高田:うん、やっぱりここに書いてあることがすべてというより、これを通じて自分の記憶を引き出せるみたいなところはありますね。そういう意味では、色々な書き方を工夫してみたらいいんじゃないかなと思います。
A:フィールドの魅力についてもう少し教えてください。写真をいくつかみせていただけますか。
高田:この写真は、この直前に結婚式があったんですけど、その結婚式を僕も手伝って町の教会まで花婿と花嫁を連れて行って、一緒に帰って来ました。その数日後に村の子どもたちが結婚式を演じて遊んでいたところです。花婿と花嫁の恰好をした人とか、それをお祝いするような花束を持っている人とかがいて、みんなで行進しながら歌を歌ったりダンスのステップを踏んだりして花嫁や花婿をお祝いします。これ花嫁役が2人いるんですけど、実はもう一人男の子で花婿役もいたんです。だけど、その男の子は嫌だったのかすぐに花婿の恰好をとって逃げてしまいました。「結婚式ごっこ」みたいな感じですよね、日本で言ったら (写真9)。あっという間にその辺にあるものを使ってこういう舞台を作っているのが面白くて、写真とかビデオを撮りました。サンは子ども集団で遊ぶというのが特徴です。2,3歳から14,15歳くらいまでの子どもが一緒に遊ぶことが多いんです。市販のおもちゃはほとんどないんですけど、色々なものを自分で作ったり色々な遊びを自分達で考え出したりというのがすごく多くて、それが面白いなと思って見ていた記憶があります。Aさんもその辺りに関心を持っているんですよね。

A:こんな風に大人の真似をすることはよくあるんですか?
高田:よくありますね。この時は結婚式ですけど、それ以外にも学校ごっこなんかすごく良くやっていました。皆学校ごっこの時だけは、先生役になりたがるんです。先生の役をして皆を怒ったり、小さな木の杖でピシピシと叩いたりします。子どもが楽しんでそれをやっているのが面白いですね。あとはこっちの写真はナミビアのサンの子どもですね(写真10)。あ、一つ前の結婚式の写真もナミビアのサンのものです。結婚式もキリスト教と農牧民の慣習の入り混じった感じの結婚式でした。それをサンの大人がやって子どもが遊びにするというのは、子どもの目線から社会がどう見えているか、サンの社会変容とは何を意味するのだろうかと考える時にも面白いですね。こちらの写真もそれにちょっと関係していて、子どもがその辺にあった木で作ったウシや生活用水用の井戸のおもちゃです。この地域はボツワナと違って農牧民と長い間密接に関わりながら暮らしているので、サンの所有しているウシは少ないんですけど、農牧民のウシはたくさんいます。生活用水も井戸水からとっています。ほとんど材料はないと思うんですけど、かなり精巧に作っていますね。クルクル回すと、ちゃんとバケツになっているところが上がっていくようになっていて、水もちょっと入れたりしていました。こういう井戸はボツワナだったらほとんどないタイプのものなので、この地域の特徴が出ていていると思います。そうやって子どもが大人の社会の特徴や変化をどう捉えてどう自分の中で消化していくのかというのは、今も面白いなと思っているテーマです。

A:アフリカの子どもと日本の子どもで大きく違うと感じる点はありますか?
高田:色々なところで違いはあると思います。僕は大学院生の時は発達相談員などで日本の保健所とか養育センターを通じて地域社会の子どもにアクセスしていました。その後、自分にも子どもができて子育てを自分でやるようになりました。限られた側面からだけど、日本と南部アフリカの双方で子育てを見たり実践したりということをやってると、違いも共通点もたくさん見えてきますね。違いとしては、まず子ども同士の関り方はすごく違う感じがします。サンの間では、地域のコミュニティが密な関係を持っていて、コミュニティの中の幅広い年齢の子どもがずっと関わり続けます。日本では地域の規模がずっと大きいので、同じ市町村に住んでいても知らない子はいっぱいいると思うんですけど、ボツワナでもナミビアでもコミュニティの中だと子ども同士は皆お互いよく知っていて、物心がついたころからよく一緒に遊んでいます。あと日本だと、学校が始まると同学年の同じ年齢の子どもで遊ぶことが多いですよね。いっぽう、ボツワナもナミビアも年齢幅の広い子が密な関係を作りながら育っていて、かつ自分の年齢が変わっていくにつれて段々と人は入れ替わっていきます。僕がボツワナやナミビアのサンと関わり続けて20年以上たちますけど、今行っても昔見たような遊びをやっていたり、役柄が入れ替わって前は教わる立場だった子が教える立場になったりということはすごく良く見ます。その中で子どもの文化というものがずっと維持されているようなのがすごく面白いなと思います。日本でも子ども文化みたいなものはあると思うんですけど、社会の規模とか、関わる年齢幅とかによってずいぶんあり方が変わるかなと思います。そういうのも面白い研究テーマでしょうね。
A:遊動生活をしてた時と定住してからは変わった印象ですか?
高田:変わっていると思います。ここの写真にのっているナミビアの場合は、定住生活してからかなり長いんですけど、ボツワナの場合は比較的最近に再定住が起こって、かなり遊動的に生活していた人達が一か所に1,000人以上の人が集住することになりました。そのため、遊動時代の影響はボツワナの方が強く残っている感じがあります。遊動しているとキャンプ自体がどんどん離合集散してメンバーが変わっていきます。その中でも、親しく関わる人達はついたり離れたりしながら一生関わるという形です。集住することでより多くの複数の遊動グループが一か所に住むことになりました。子どもはその辺は大人よりも意識しないで違うグループの人達と遊び始めるので、関わる人の幅は定住した後の方が広がっているなという印象がありますね。あとは遊びの種類も変わってきました。
A:どんな風に変わってきているのですか?
高田:例えば、こういう定住に関わる井戸みたいなものは定住したことによって増えたし、それに使うコップみたいなのものやこういう毛糸の紐みたいなものも、例えば田中二郎先生が調査していた頃の遊動生活ではかなり希少価値があって落ちてなかったと思うんですけど、定住地だと子どもが拾い集めてくるようになっています。逆に定住生活が長いナミビアの方だと野生動物を見る機会が少ないんですね。大人が狩ってきて肉になった動物は見る機会はそれなりにあるんですけど、生きている野生動物を見る機会はぐっと頻度が下がる。遊動生活の中では、女子は割と早い時期、子どもの時から女性の採集活動に参加するんです。やっぱり採集に行くことで見聞きして知ることはすごく多いんですけど、それが定住してさっきみたいな農牧民の家に居座るみたいなことが盛んになると、そこでする経験はずいぶん変わってくるんじゃないかなと思います。
A:サンはどのように狩猟するのですか?
高田:狩猟に関してはね、昔から研究者の主要な関心事だったので色々なことが調べられています。これはボツワナのサンの1970年代くらいの田中二郎先生の写真です。キリンの猟をした時の写真ですね(写真11)。今はもうキリンは完全に禁猟なんですけど、当時はまだ狩ることができました。Aさんの行っている熱帯雨林とは違ってサバンナ植生なので景観はここにあるような感じです。カラハリ「砂漠」とはいっても木は生えているんですけど、見晴らしはかなりいい方ですね。主要な獲物も植生によって色々変わりますけど、キリンみたいな警戒心の強い動物に近寄って行くのは大変ですよね。「伝統的」な狩猟と言われているのは、徒歩でなるだけ接近して、毒の塗られた弓矢をまずは当てるという作業が必要です。その射程距離は短いので、矢を当てられる距離まで動物に気づかないように近づくというのはシンプルだけど熟練した技術を要します。風下から抜き足、差し足で近寄っていくという作業ですね。矢が当たっても毒性はそれほど強くないので動物をまずは逃がすんですよね。逃げた後の動物の足跡をたどって動物を追跡するという過程がその後に続きます。それを可能にするためには環境のこと、動物のことをすごくよく知らないといけません。動物の残した足跡や血の跡をたどって、場合によっては数日間追跡します。これに対する関心が、僕の研究テーマの1つの道探索というテーマに繋がっていきました。そこには彼らの色々な知識のあり方や環境の見方が反映されてます。追跡に成功すると毒矢が効いてだいぶ弱っている動物に遭遇することになります。そこで追跡グループの人達は犬をけしかけたり槍を使ったりして動物にとどめを刺すという形ですね。これが1980年代くらいになるとウマを使う猟が増えました(写真12)。共同研究者の池谷さんや大崎さんがずいぶん詳しく調べられています。実は、ウマ自体は時期や地域によってはもっと早くから導入されていたことが後々分かってきました。いずれにせよウマを使った猟と徒歩で弓矢を使った猟は全く違う様子を示します。ウマを使った猟では、ここにあるようにウマとロバに荷物を運ばせて、狩猟チームを作って狩りに行きます。ウマの機動力はほとんどの大型アンテロープよりも高いので、非常に効率よく猟ができるようになったことが示されています。ウマを使うと多い時は一日のうちに数頭のアンテロープ、ゲムズボックやエランドなんかが仕留められることもあります。そのため、狩猟の仕方だけではなくて、その後得られた肉の分配の仕方や流通の仕方までずいぶん変わったことが知られています。ウマを使った猟の場合は最初から鉄製の槍を持っていて追い詰めたアンテロープを仕留めるというような形ですね。ただし、ウマを使った猟の時も、この景観を見てもらったらわかると思うんですけど、非常に平らな地形でかつ動物は広い範囲を動くので、狙いを定めて正確に追いかけて仕留めてまた自分のキャンプに帰るためには、環境に対する知識がすごく重要です。ウマが入ってきてからウマを使った猟はみるみると広まったので、徒歩で弓矢を使った猟と共通する環境の見方が生かされていると思います。彼らの柔軟性とそこに通底している環境や動植物との深い関わりはすごく面白いテーマだなと思っています。ピグミーとはまた全然違う形で実現されているとは思うけど、狩猟採集民として通じるとこもきっとあるよね。


A:たぶん…、サンのことはちょっとまだよくわからないですが…。
高田:ある程度経験を積んだ後に、別の人が行っているフィールドに行くと発見が多いと思います。僕も去年初めてカメルーンのバカ・ピグミーの村に行ってすごく面白かったです。ぜひ院生さんも他のフィールドに来てもらったら面白いと思います。
A:はい!子どもはどのように狩猟の技や動物の知識を身につけていくのですか?
高田:これも子育て研究では大きなテーマになっています。まず狩猟採集民研究の中でも、どうやって狩猟採集の知識を身に着けるかというのはかなり早い時期から関心がもたれたテーマです。初期の研究から分かってきたことは、あまり積極的に大人が子どもに教え込んだりしないのではないかという議論ですね。僕も割とそれに近い印象を持っているんですけど、手取り足取り狩猟や採集の仕方を教えるということはほとんど見たことがないです。たださっき見たような小さい子どもでも狩猟や採集には関心を持っていて、自分の遊びの中でそれに関わる模倣をしてみたり、男の子なら小さい弓矢を作ってキャンプから近いブッシュで小動物やトリなど狙って狩りをしたりします。女の子だったら模倣の遊びだけじゃなくて、早ければ5歳くらいから遅くても10歳くらいから大人のグループに一緒について採集に行って、その中で色々なことを徐々に覚えていくという特徴があります。採集は狩猟と比べて危険が少ないのでこれが可能になっています。いっぽう、狩猟は成功率が低くかったり、ウマの猟だったらウマを乗りこなすテクニックやチームで動物を追い詰めたりすることが重要になったりするので、狩猟のチームで一人前の役割を果たすのは中々大変です。実際にそこに参加し始めるのは10代後半になってからが多いと思います。そこでもいちいち教えるのではなく、活動に参加しながらだんだんスキルを上げていくみたいなことを長い時間をかけて行います。そういう特徴があるということが色々な狩猟採集社会で記述されていたんですけど、最近はそれを動画に撮って、具体的にそんな教えていないといってもどういう形で学びが可能になっているのかというのをミクロな相互行為の分析の中で考えていこうというのが研究の大きなテーマになっていますね。
A:親から教わることが多いんですか?それとも他の人から学んだりもしているのですか?
高田:色々なタイプがありますね。大きく分けると親から子という垂直方向と言われる学びと、親以外の大人から次の世代が学ぶという斜行方向と、同世代という水平方向によく分類されますけど、サンではどのタイプもありますね。活動によってどの関わりが重要かは変わってきます。今言った水平方向、垂直方向、斜行方向というのが具体的にどういう場面でどういう形で達成されているかは、ここ最近、あるいはこれから先の大きな研究テーマだなと思います。
A:初めてフィールドに行ったときの様子と最近のフィールドの様子を比較して、変化はありますか?
高田:はい。さっき言ったように僕が最初にフィールドに行ったのは1990年代の後半なんですけど、そこから今、だいたい四半世紀くらいたっていますよね。その間色々な変化があったんですけど、ボツワナのフィールドだったらちょうど再定住した後に行っているので、定住化してからの4半世紀には一言で言えないぐらい、彼らの歴史の転換点とも言うべき多くの変化がありました。とくに生業活動や人間関係を始めとして、一か所に大勢の人が住むようになったことに伴って変わったことは多いですね。
ナミビアの方は、僕が行った90年代後半は独立してから10年後くらいなので、新しく国を作っていこうという雰囲気の中でどんどん村が開発されていく過程がこの20数年間続いている感じです。例えば町へのアクセスがすごくよくなったり、都市と地方の移動のパターンも大きく変わったりということがすごくありますね。これは村だけじゃなくて国全体のインフラの整備だとか携帯電話をはじめとした色々な通信に関わる機器の発達もすごく影響していると思います。そういう変化は僕も実感しながらフィールドワークを続けてきました。面白いなと思うのは、サンの研究では僕が行く前の時期の記述も結構されているわけです。1960年代くらいの記述は僕の指導教員の先生のものもあります。さらに歴史的な文献を遡れば、1世紀から2世紀前のサンの姿も記述されているので、自分である程度の変化を経験したら昔の記述がより面白くなってきました。例えばこの写真に映っているのはンガミ湖というボツワナの北西部にある湖です(写真13)。これは、ずいぶん昔の1800年代終わりや1900年代初めの文献にも出てくるようなところで、「消える湖」と言われていたんです。ある探検家が行ったときはものすごい水をたたえていて、そこに地上のパラダイスみたいに大型獣も小型獣も集まってくるような記述がなされてたんだけど、次に別の人がそこの場所に行ったらもう全く何もなくって砂漠になっていたという記述があるようなところなんです。この地域というのはオカバンゴの湿地帯というのもあるので、地下水脈と地上の水の移動がかなりダイナミックに生じるところです。地下の水の分布と雨として降る水とアンゴラの方の大きな川から流れてくる水が複合的に関わって面白い動きをします。僕が2000年代に行った時はこういう形の割と湖の状態になっていて、楽園とは言いにくい状態ですけど、すごくたくさんのトリがここに生息していて面白かったです。こんな光景を100年以上前に書かれた民族誌の記述を思い出しながら見ると、自分のフィールドワークの経験も含めて、また違う味わいがあるなという気がしました。たぶん先輩方、例えば伊谷純一郎さんだったらここで俳句を詠むと思うんですけど、僕は技術がなかったので写真を撮って思いをはせました(笑)

A:面白いですね。
高田:変化って、目に見える変化もあれば、段々時間を得ることで分かってきた変化もありますね。逆に変化しているように見えて変わらないこともあると思います。そういうことを考えるのは、一つのフィールドに継続的に行く面白さの一つかなと思います。
A:高田さんは子どもの歌と踊りについても調べていますが、どうして歌と踊りを取り上げたのですか?
高田:これはAさんとも重なるテーマですね。まず子ども達にとって歌と踊りがすごく大事でかつ長い時間関与する遊びだというのが大きいですね。子どもはすごく頻繁に歌ったり踊ったりしているというのは、初めて訪れたときから続いている印象です。研究としても面白いテーマはたくさんあって、例えばなんどか述べたような色々な年代の子ども達が一緒に活動するというサンの大きな特徴を考えた時にも、歌と踊りはそれにすごく適している活動ですね。会話は全然成り立たないような10代の子どもと2,3歳の子どもも歌とか踊りだったら一緒に遊べます。色々な人が出たり入ったりしながら関わることもできるし。サッカーみたいな遊びだと、ある程度運動能力、身体的な力が拮抗していないと面白くないと思うんですけど、そういう制約もあまりありません。歌と踊りだと、どんどん新しいバリエーションや創作も可能になるので、既存のおもちゃみたいなのが無いからこそより発達するのかなと思います。僕は、子育てとか道探索とかエスニシティといった研究テーマを繋ぐ視点としてコミュニケーションにすごく関心があるんですけど、コミュニケーションという視点から見ても歌と踊りは面白い活動のジャンルです。分析をするのは一筋縄ではいかないところもあるんですけど、ずっと興味を持ち続けています。これは踊っているところですね(写真14)。

A:楽しそうですね。
高田:この子(中央で踊っている少女)は8,9歳くらいだと思います。この子(中央で拍手をしているオレンジ色のスカートを着ている少女)はもっと大きくて10代半ばくらいになっていますかね。この子(中央に座っている緑のシャツを着ている娘)なんかは10代後半になっていて小さな赤ちゃんの子守をしています。端っこの方ではいたずらっ子ぽい男の子(左手の緑のシャツを着ている少年)がそれを茶化そうとしていて見ています。この一枚の写真でもそれぞれの子どもがずいぶん色々な関り方をしているなというのが見えますね。Aさんのフィールドに行っても色々なバリエーションで色々な遊び方があるなと感じました。遊びは研究の対象として面白いですね。
A:歌と踊りも時代の変化を受けていますか?
高田:結構ありますね。子どもは新しい歌や踊りを覚えるのが大好きです。自分で違うバリエーションを作ることもあります。あと、色々なところではやった歌と踊りを誰かが聞いてくるとぱっと広まるということもよくあります。それを反映しているのかどうかよく分からないですけど、学校で教わった歌と踊りだとか、選挙のキャンペーンで政党の事務所が子どもに伝えた政治的なメッセージのある歌がはやったこともありました。後者は政党がそれをはやらせて選挙運動につなげようとしたんだと思います。子どもはそうした意図は気にしてなかったと思いますけど。歌と踊りから見えてくることも色々あるなと感じました。
A:フィールドワークにおいて、大事にしていることは何ですか?
高田:まずはどんなフィールドワークも、色々な人との関わりの中で可能になることだと思うので、参与観察させていただく現地の人達との関わりが大事ですね。フィールドワークは研究だけの関わりだとは言いにくくて、自分自身の人生の重要な一部になっているところがあると思います。現地の人達とも何十年間もの付き合いになるので、今もフィールドに行くと「帰ってきた」という感覚を覚えます。そういう関係を作ったり維持したりしていくには、フィールドワークに限らないとは思うんですけど、関わる人に対してのリスペクトが大事ですよね。それからできるだけその人達の目線に沿うこと、日本で言うと共感ということになると思うんですけど、それが大事だなと思います。その一方で、フィールドワークはそこに引っ越すというのとは違うところがあって、日本とフィールドと研究発表する研究者のコミュニティを移動しながら、論文を書いて、書いた後それに対するやり取りをしてという過程があります。その中で、自分自身で違う状況を移動するという余地を残しつつ、さっき言ったリスペクトと共感をずっと持ち続けること、その辺のバランスがすごく大事な仕事なのかなという気がしますね。
A:最後にアフリカ専攻を志望する人へのメッセージをお願いします。
高田:今まで言ってきたことのまとめみたいな感じにはなりますが、アフリカ地域研究は研究ではあるんですけど、すごく生活とオーバーラップする研究分野なんじゃないかなと思います。ASAFASでは、少なくとも五年一貫制の過程の中でかなりの長い期間をフィールドで過ごします。大学院生時代というその人の人生の中でも大きな変化や意思決定が必要な時期にそれをするのはすごく大きなことだと思います。さっき積極的ワークホリックという言葉を使いましたけど、僕はそれにはいい面が多いなと捉えています。いいかえれば、自分の人生の中での重要なパートをフィールドの人達と共有する、フィールドの人達の人生とオーバーラップした時期を過ごす経験を持つという、かなり特殊な研究分野だと思います。研究としての面白さだけではなく、人生の選択としてもすごくやりがいがあるんじゃないかなと思っているので、ぜひそういうことに関心を持つ人にドアを叩いてほしいですね。